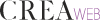38歳独身女性、築45年団地暮らし…「しあわせは食べて寝て待て」は令和のグルメドラマの新展開?《ロンバケとの意外すぎる“共通点”も》

「生産性」や「タイパ」といった言葉が世を席巻し、常に効率や成果を求められる現代。息苦しさを感じる日々の中で、私たちは一体何に「しあわせ」を見出せるのだろうか? その問いへの温かな答えを、NHKドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』は静かに語りかけてきます。
「よくあるグルメドラマなんじゃないの?」を裏切る良作
本作は、膠原病という難病とともに生きることになり、仕事を変え、団地に越してきた38歳独身の主人公・麦巻さとこ(桜井ユキ)が、新たな人間関係と「食べること」を通して、しあわせとは何かと気づいていく物語。
よくある「グルメドラマ」なんじゃないの? 最初はそう思った人もいるでしょう。もちろんフードスタイリスト・飯島奈美さんが手がけているおいしそうな料理はどれも魅力的で、観ていてこちらまでお腹が空くようなシズル感たっぷり。加えて、食がもたらすポジティブな体験(人間関係の広がりとか)や料理を巡る人間ドラマもしっかり描かれています。
でもそれだけじゃない! 本作は「食」をエンタメや人間ドラマのツールとしてだけでなく、人生を支えるための実質的な行為として深く掘り下げているんです!
このドラマが大事にしているのは、健康を維持・増進するための行為としての食事です。当たり前過ぎて、普段は見過ごされがちな食事の側面を、本作はあえて丁寧に描いてくれています(同様の点で朝ドラ『おむすび』も評価したい!)。
特にドラマで重要な役割を果たすのが「薬膳」の知識です。病気によって、仕事や住まいを失い、将来への不安を抱える麦巻にとって、薬膳は心強い味方。「頭痛の時に大根をかじる」なんていう、手軽に真似できる知識が多く得られるところもポイントです。食べ物で症状が改善しても、それは良い条件が重なったからかもと、むやみに効能を謳わないところにも好感が持てます。

麦巻が最初に食事の大切さを実感したきっかけは、隣の部屋に住む司(宮沢氷魚)が作ってくれた「肉団子と野菜のスープ」でした。レシピによると、スープはれんこんのすりながし入り。薬膳では、れんこんはのどや肺を潤すと言われています。とろみがあって冷めにくいし、胃への負担も軽そう。さらに、具のしめじは免疫力を高め、キャベツは胃腸に良い。なるほど、具材はすべて理にかなった組み合わせです。
食事を、自分の体に入れる食材ベースで考えると、「食事=自分自身の体とじっくり向き合い、労わるための大切な時間」へと質を変える。このドラマを見ていると、「食べる」という行為に、深い意味や効能が宿っていることを気づかされます。
令和の静かなブーム「団地モノ」としての魅力
麦巻が引っ越してきたのは、築45年、家賃5万円の古い団地。そう聞くと「古い」「お年寄りが多い」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、近年はリノベーション物件が増え、広めの間取りなのに手頃な家賃、昭和レトロな雰囲気、敷地の広さゆえの日当たりや風通しの良さなど、多くの魅力が見直されています。

さらに最近注目されているのが、団地を舞台にしたコミュニティ。世代を超えたつながりを生み出そうという動きも増えていて、NHKの『ドキュメント72時間』の団地回は高い人気を誇ります。
ドラマでいえば、50代、独身、実家暮らしの、団地で生まれた幼なじみのふたりの気ままでユーモラスな暮らし、さらりとした友情に共感が集まった『団地のふたり』のヒットも記憶に新しいところ(実は本作と同じロケ地という共通点も!)。特別な冒険も感動もあるわけではない、日記に記すほどでもないような日々だけど、そんな日々が愛おしいのだと、ほのぼの感じられる作品でした。
本作もまた、団地という場所だからこその「つながり」が際立っています。大家の鈴(加賀まりこ)は司を息子のように思っていますが、もし都心のマンションの希薄な人間関係の中で出会っていたら、「え、あの人若くてニートで居候なの!?」と、司に対してもっと驚きや疑念を抱いたかもしれません。でも、いろいろな交流が自然に行われる団地だからこそ、身構えずにすんなり受け入れることができるのです。
団地の住人たちは例に漏れず魅力的。高齢者の安心な住環境づくりは大きな課題となる中、孤立・孤独が叫ばれる現代において、司のような存在がいることの安心感は計り知れません。90歳とは思えないほどパワフルで、趣味で作っている洋服や小物のネット販売までこなす鈴さんも素敵だし、イラストレーターの高麗(土居志央梨)や高校生の弓(中山ひなの)など、回を重ねるごとに麦巻の交流の輪が広がっていく展開も楽しみの一つです。

個性豊かな住人たちとの間に生まれるのは、プライベートに過度に踏み込まず、でも困った時ときはそっと手を差し伸べ寄り添う、そんなゆるやかで温かい「つながり」です。
どこか懐かしくて、物理的な距離も心理的な距離も近い団地のコミュニティは、病気で孤立しがちだった麦巻にとって、まさに新しい「居場所」。現代社会で希薄になりつつある、人とのつながりの価値を、本作は力強く感じさせてくれます。
恋愛を差し引いた『ロンバケ』なのでは
作中で特に印象的だったのが、4話で編集者の青葉(田畑智子)が言った「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉。青葉さんはそれを「できない自分を認める能力」と言い換えていました。これは、すぐに答えが出ないような状況に耐えたり、焦らず、慌てず、その宙ぶらりんの状態を受け入れていく力のこと。先が見えないコロナ禍において、その重要性が注目された概念でもあります。
たとえば、病気の経過が見えないとき。家族との関係がギクシャクしているとき。あるいは不安や孤独の正体がわからないとき。すぐに「白黒つけよう」「解決しなくては」と奔走するのではなく、一度立ち止まり、その状況をありのままに受け止めてみる。
ネガティブな感情も人間の一部として認めるということは、完璧ではない自分自身を受け入れることでもあります。大事なのは、そんな自分に焦りを感じても、決して投げやりにならないこと。その感情の波の中に、しばらく留まって耐える勇気を持つことなんです。

実は、この「ネガティブ・ケイパビリティ」に通じる名台詞が、あの伝説の月9ドラマ『ロングバケーション』にもありました。
瀬名(木村拓哉) 「何をやってもうまくいかないとき。何やってもダメなとき。そういうときは、言い方変だけど、神様がくれたお休みだと思ってさ、無理に走らない。焦らない。頑張らない。自然に身を委ねる」
南(山口智子) 「そしたら?」
瀬名 「よくなる」
南 「ほんとに?」
瀬名 「たぶん!」
タイトルにも通ずる、ドラマの核となる台詞です。これを読んでみなさんも、『しあわせは食べて寝て待て』って恋愛を差し引いた『ロンバケ』じゃん! って思いませんか? どちらの物語も、物事が明確でない、あるいはうまくいかない「不確実な状態」や「未解決の状態」を、安易に否定したり、無理に変えようとしたりせず、ある程度受け入れる姿勢を示唆しています。
そして焦って手っ取り早い答えに飛びつくのではなく、時間がかかってもいいから疑いの中に留まる心の余裕や、待つことの重要性を物語っています。
これは現代社会で推奨されがちな、効率よく成果を出す「生産性」や「タイパ」といった考え方とは正反対ともいうべき価値観です。効率だけを追求しても、真の意味ではより良い人生につながらないのかもしれない。AIに質問すれば自分にとって気持ちの良い回答をくれる時代だからこそ、すぐに答えが出ないモヤモヤの中に、一人で安心して浸れる時間を意識的に持つことが、実はすごく大事になってくるのではないでしょうか。
無理に答えを見つける必要なんてない。むしろ悩みや葛藤といったモヤモヤの中にこそ、生きる意味や自分自身の本当の願い、しあわせ、やりがいへと導いてくれる「羅針盤」のようなものが隠されているのかもしれません。
タイトル「食べて寝て待て」に込められた、納得の意味
本作のタイトルは、良い結果は焦らず待っていれば自然に得られるという「果報は寝て待て」ということわざに由来したものでしょう。ドラマの中で、主人公の麦巻や周囲の人々がおこなっているのは、「食べて」「寝て」という、シンプルで根源的な営みです。
ここで特に重要な意味を持つのが、タイトルにある「待つ」という行為。麦巻は病気の根本的な解決や劇的な回復を急いで求めていません。日々の生活を丁寧に送りながら、体の声や心の声に耳を傾け、ゆっくりと状況が変化するのを待っています。
これはまさに、「不確実で未解決な状態」の中に立ち止まり、性急な結論(=完治、あるいはそのための画期的な治療法)を求めないという意味で、先ほど述べた「ネガティブ・ケイパビリティ」の実践そのものです。
自分ではどうすることもできない状況(病など)をまず受け入れること。そしてその中で、「食べる」「寝る」という、今の自分にできる最も基本的なセルフケアを大切にすること。それこそが、穏やかなしあわせを感じるための確かな土台となるのです。
そして、「待て」という言葉が示唆するように、しあわせを追いかけ回すのではなく、日々の暮らしを丁寧に積み重ねていけば、自然と見えてくる自分らしいしあわせの形があるのではないか。
麦巻さんのささやかな日常が、変化を急がず、自分自身を労わる時間がいかに大切か、そして「待つ」ことの中にこそ見つかる真のしあわせがあることを、私たちに優しく教えてくれているのです。さぁ、今日は何を食べようかな。
文=綿貫大介
写真=NHK
あわせて読みたい
-

- ぶっちゃけすぎて友人がドン引き?貧困と闘った子ども時代のこと/東京のど真ん中で、生活保護JKだった話(1)
- ぶっちゃけすぎたか / (C)五十嵐タネコ/KADOKAWAたび重なる父親の病気、そして母親も療養中といった理…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS,スローライフ,健康]
-

- 仕事から疲れて帰ると、おにぎりがテーブルに。息子の優しさに涙が止まらない
- 「ママのごはん」 / (C)お腹すい汰/KADOKAWASNSで話題沸騰中の「ちゃんぺんママぺん」シリーズ!平日は…
- (レタスクラブニュース)[手作り,自然化粧品]
-

- 新宿マルイにタイハーブティー専門カフェが登場
- プレミアムオーガニックハーブブランド「アバイブーベ」の正規代理店であるアバイブーベジャパン株式会社…
- (美容最新ニュース)[健康食材]
-

- 配属ガチャにハズレたうえボーナスは0.1カ月分!?こんな会社は意外と多い?カオスな業務サバイバルを乗り越えた実話記録【作者に訊いた】
- 220人の会社に5年居て160人辞めた話 / 画像提供:かっぱ子さん(@kappacooooo)実は、こんな会社って多いの…
- (Walkerplus)[秋グルメ]
-

- 室積に布作家のアトリエ兼雑貨店 ジャガード織りの布小物や雑貨を販売
- 「モロー雑貨店」(光市室積5)が4月22日、海商通りの「海商館」跡近くにオープンした。(周南経済新聞) …
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]
-

- ピーマン大量消費、一度に食べ過ぎるのは体に悪い?【大学教授が解説】
- 【大学教授が解説】ピーマンを一度に食べ過ぎると、腹痛や下痢が起きるリスクがあります。胃腸の弱い人は…
- (All About)[野菜,レシピ]
-

- 京都・洛北の青もみじプチトリップ、叡山電車に乗って「下鴨神社」から京の奥座敷「貴船」へ♪
- 5月になると京都はもう初夏の気配。青もみじのシーズンがやってきましたが、まだまだ知られていないスポッ…
- (ことりっぷ)[まちグルメ]
-

- 気になる人のあの本、あの曲、あの味〈第1回:石崎ひゅーい〉|「石崎家の留守番電話は、この物語の朗読だったんですよ」
- 石崎ひゅーいのあの本、あの曲、あの味新曲『HERO』をリリースし7月にワンマンライブ「石崎ひゅーい LIVE …
- (CREA WEB)[CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.