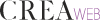「NCTジェヒョンさんは年下だけど尊敬できる人」イ・ユンソク監督が『6時間後に君は死ぬ』に込めた“祝福”
ある男の予言によって突然、死を告げられた一人の女性。タイムリミットは6時間。死へのカウントダウンがはじまったいま、殺人鬼を見つけ出し運命を変えることができるのか――。高野和明の同名小説を韓国を舞台に映画化した、『6時間後に君は死ぬ』のイ・ユンソク監督にインタビューした。

――この映画の成り立ちについて教えてください。
イ・ユンソク 7年くらい前から原作の版権を買って制作会社が映画化に動いていたんです。何人かの監督と話をすすめていたのですが、そこから6年くらいしたときに私の方に監督としての話が来ました。そのときにはもうキャスティングも決まっていて、何人かの監督によって脚本も形になっていました。自分が監督をすることになってからは、原作を膨らませる方向で脚色していこうということになり、原作の構成を残しつつ、韓国の社会背景や現状を描きながら、韓国映画として成立する方向を目指しました。
――映画を見ると、韓国の格差社会などが反映されているなと思いました。
イ・ユンソク 原作小説(著:高野和明)が発表されたのは、今から10年ほども前なので、例えば携帯電話ひとつとっても今とは違いますし、経済状況も違います。その上、日本と韓国でも違っていますよね。だから、まずローカライズをして、韓国の社会背景などを描かないといけないと思いました。その中で自分が一番大事だと思っているのが、朝鮮族の男性キャラクターが登場するシーンです。この朝鮮族のキャラクターの設定の違いから、韓国の現状を伝えられればと考え、構成していきました。

――朝鮮族の男性は、延辺出身で、韓国映画を見ている人ならば、『哀しき獣』や『新しき世界』『犯罪都市』などにも出てきているのを知っている人も多いと思います。これらの映画の中に出てくる朝鮮族の人物は犯罪と繋がっていましたが、本作の中では、ヒロインのジョンユンとの間に、シンパシーが生まれる部分もあって印象に残りました。
イ・ユンソク 原作では地方から上京した男性という設定で、バスターミナルから自分の田舎に帰るという部分は同じです。映画の中では朝鮮族の男性が自分の故郷に帰るという設定にしました。というのも、ジョンユンというキャラクター自体が、地方から上京してきてアルバイトで苦しい生活をしていて、社会のシステムの中に入れない人物として設定したので、彼女よりもさらに社会のシステムに入れない人物を登場させることによって、マイノリティ同士の中にも偏見があったりすることを描こうと思いました。
韓国では、朝鮮族の男性は、その属性だけで犯人扱いされるような偏見もまだ残っています。内なる偏見は誰の中にも存在するものかもしれないということに気付いてほしいと思って描いたんです。
――映画の中には、ミソジニーを持った男性像も描かれていました。
イ・ユンソク 原作にもそういう考え方は書いてありましたが、韓国での映像化にあたって、セリフを加えたりしました。そして、ジョンユンは、その人に対してどのように対峙するか、その考え方の誤ったところを話しています。
NCTジェヒョンのスクリーンデビュー作品
――主演をつとめた、NCTのジェヒョンさんのことも教えてください。ジェヒョンさんにとって映画デビューとなる作品です。
イ・ユンソク これは他でも言っているんですが、ジェヒョンさんのキャスティングに関しては、自分が名前をあげたわけではなくて、会社の意向ですでに名前があがって、そこから彼のことを知っていきました。彼は芝居の経験は少なくて、撮影したドラマも最近、放送されはじめたばかりなんです。なので、MVを見たり、バラエティやYouTubeなどでトークをしている部分を見て、彼の人となりを知りました。
実際に顔合わせの段階で、部屋に入ってきた彼を見たとき、もちろんアイドルをやっているときのようなかっこいい姿ではあったんですが、年相応な青年だと思いました。普段の生活の話をしたりしてみて、ミステリアスなところもあるけど、人の痛みが見える主人公のジュヌを演じてもらえるなと実感したし、そういう表現ができる人だと思えました。そして、ジェヒョンさんがキャスティングされたことで、この映画が実際に動き出した部分があるので、感謝しかありません。

――現場ではどんな人でしたか?
イ・ユンソク マイペースで動じないところがあります。アイドルとしていろんな経験をしてきたということも関係あるのかもしれません。スタッフさんやファンの方にもフレンドリーで、働きやすい環境を作ってくれました。気配りも素晴らしいし、自分より随分年も下だけど、尊敬できる人だなと思いました。
――監督はもともと日本で映画を学んでいたそうですね。どのようなきっかけがあったのでしょうか。
イ・ユンソク 自分が日本に映画を学びに来たのは2004年で、韓国映画が上り調子になっていたころでした。ただ、その頃は、韓国では映画を作るときに標準契約書が交わされるような時代ではなかったんですね。その頃、たまたま映画祭で日本の監督と話をしたときに学校を紹介してもらって、当時働いていた会社をやめて日本に留学しました。もともと自分は日本文学を専攻していたので、成瀬巳喜男や小津安二郎の映画をたくさん見ていたんです。大学生の頃も、岩井俊二監督の『Love Letter』や是枝裕和さんの作品を見ていたこともあり、日本で勉強してみたいという気持ちがあったんです。
――最近、韓国の映画監督にインタビューをすると、日本映画への関心が強くなっている印象がありますが、イ・ユンソク監督も感じるところはありますか?
イ・ユンソク 今の40代くらいの韓国の監督は、1990年代に日本の文化が解放されて、その頃に青春を過ごした方たちが多いんです。自分もその世代ですが、そんなことも関係しているのではないかと思います。特に、少し年齢は上になりますが、ポン・ジュノ監督も日本のアニメや漫画が大好きですよね。

それと同時に、今の韓国の映画業界は商業作品に集中していることがあって、インディーズ映画が弱いんですね。最終的には映画監督も生活していかないといけないので、インディーズでデビューしても商業監督にならないといけないということがあります。
日本は今年もカンヌ映画祭で、コンペティション部門に『ルノワール』が入っていますよね。濱口竜介監督にしても、黒沢清監督にしても、国際的に評価される日本映画は、商業的なものではない作品が監督主導で作られているなと思います。韓国も監督主導のものもあるけれど、基本は製作者主導だから、そういう違いが生まれてきているのだと思います。
今一番うれしいことは、次の作品が撮れるということ
――監督は、日本と韓国を見ながら、作りたいものをどのように作っていこうと思われますか。
イ・ユンソク 自分は、作りたいものがあれば、商業でもインディーズでもどちらでもいいと思っています。でも、韓国に戻ってきたからには商業ベースでやらないと成立しないところはあって、一本目を作ってみて、予算を回収する難しさは至難の業だなと感じているけれど、それでも、回収できるようにしていきたいと思っています。
私自身も、三宅唱さんや濱口竜介さんや黒沢清さんが好きで、そのような映画が作れればいいなと思いつつも、商業監督として、毎年映画を撮っていきたいと思うし、その中のフィルモグラフィーの中で、評価されるものが作れればいいなと思っています。今は生き残るための映画をとって、次も準備して完成したらまた次を撮りたいです。

監督だから、自分の撮りたいものをとって評価されたい気持ちもあるけれど、今一番うれしいことは、次の作品が撮れるということです。今はあんまりこういう路線で行こうというよりも、続けていけば評価される作品も撮れるだろうしという感覚です。
――今後も、日本でも作品を撮りたいという思いはありますか。
イ・ユンソク 映画が最終的に成立するためにはいろんな過程があるので、今年準備すればすぐに撮り始められるではないんですね。今は6月からクランクインする新作の準備をしています。この作品にとりかかりながら、その間に次の作品も準備していて、それが日本で撮影できればいいなと考えています。今まで20年間、日本で映画の仕事をしてきたので、日本の演者さんやスタッフと仕事できればいいなと考えています。
――最後に、日本でこの映画に関心を持っている方に、一言お願いします。
イ・ユンソク ジェヒョンさんのファンの方は、映画祭にも見にきてくださった方も多くて感謝していますし、この映画の楽しみ方も知っていると思います。ファンの方にも、そしてまだ見ていない方にも、ジョンユンという女性キャラクターの生き様を見てほしいですね。私は、この映画をジュヌとジョンユンという二人のロードムービーのようにも見えるといいなと思って作りました。今を生きるために、ふたりが夜の街を旅する姿を、自分の個性として映画に入れました。そして、ふたりを祝福したくてこの映画を作りました。そんなところも感じていただけたらと思います。
文=西森路代
あわせて読みたい
-

- 悪い子は鬼に連れて行かれて毎日酢を飲まされる?伝承・迷信だらけのクリスマスを大解剖【作者に聞いた】
- 作画:尾花せいご(@seishoobi)さんと監修:西洋魔術博物館(@MuseeMagica)さんによる創作漫画「放課後おま…
- (Walkerplus)[イベント]
-

- 昭和レトロを旅の思い出に!旅先の夜を楽しむ「ニュー・ウエダ」の「ナイトパスポート」とは?
- 長野県の東部に位置する上田市では、知られざる街のディープな魅力を“上田市のB面”として紹介するプロモー…
- (Walkerplus)[旅]
-

- 【介護のピンチ、解決します!】介護サービスが多すぎる! 混乱しないでうまく活用したい
- とにもかくにもケアマネジャーさんに相談を。次はホームページを覗のぞいてみませんか? / (C)稲葉 耕太…
- (レタスクラブニュース)[田舎暮らし]
-

- 久しぶりに会った父の余命は一年。苦しめられた過去の記憶が蘇る/余命300日の毒親(2)
- 大病だからって / (C)枇杷 かな子、太田 差惠子/KADOKAWA幼い頃からひどい扱いを受けてきた。そんな大…
- (レタスクラブニュース)[ダイバーシティ,新商品]
-

- 春と夏は、“キンキンに冷えた炭酸を持ち歩けるボトル”で乾杯!【いいもの50選 〜“春夏アウトドアの名脇役”編〜】
- アウトドアのプロ18名が選ぶ「いいもの」50アイテム 穏やかな気候に心がはずむ、お出かけにぴったりの季節…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.