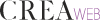神津はづきさんが語る、亡き母・中村メイコさん(89)の素顔「私はね、母に涙を見せたことがないんです、あの人は“母”ではなかったから」
『ママはいつもつけまつげ』(小学館)という本が発売3カ月で4刷の売れ行きを見せている。戦前から2023年までの長きにわたり活躍した、中村メイコさんの次女・神津はづきさんが綴った回想のエッセイ。著書に対する思いと、これまでのことを伺った。


執筆中に何十年も溜まっていた涙が出た

――お母さまの中村メイコさんは2歳から子役として活躍して、人生をほぼ女優・タレントの「有名人」として生きた人。やっぱりスケールと感覚が常人と違うなと、面白く拝読しました。はづきさんは執筆にかかって「はじめて涙があふれてきた」と、先日テレビで語られていましたね。
神津はづきさん(以下、はづき) 何十年も溜まっていた涙が出た、という感じでした。私はね、母に涙を見せたことがないんです。母の前で悩んで泣いたとか、叱られて泣いたということが本当に一度もない。あの人は「母」ではなかったから。
――えっ。
はづき 母ではなく「中村メイコ」なんです。もし私が「きょう、フラれた」なんて話をしたら、「あら!」と驚いた後に「私がフラれたときの話をしてあげるわ」って自分の話が始まっちゃう。全部次の瞬間に自分の話をする。姉(作家の神津カンナ氏)は長女だからか、「もっと自分の思う母親であってほしい」という気持ちが強かったんでしょう、母に反発もして泣き叫んでけんかもして。でもそうなると母はますます芝居がかっちゃう。「カンナッ、ママにはお仕事があるのよ、わかって!」なんて(笑)。

――はづきさんは、そんなやり取りを見て育ってきたと。
はづき 「大丈夫、このふたり……?」なんて思いながら育ちました。母に感情をさらけ出しても仕方ない、「まあいっか、それがママなんだから」という回路になっちゃった。母の前で泣いたのは「サインはV」の最終回をふたりで観たときだけ。一緒にバスタオル持って号泣しました(笑)。
「あのね……ママは変。みんなのママと違うし、みんなのママができるのにママはできないの! パパ、助けて! ママを普通のママにして!」
(中略)
「はーちゃん、何を言ってるの? はーちゃんのママは変なんだよ。普通のことは何もできるわけないし、もし普通にしなさい! って言ったら、もっと変なことになるはず。だから、諦めなさい」(『ママはいつもつけまつげ』26〜27ページ。はづきさんが4歳のときのエピソード)
はづき 父に「ママは変なんだよ、諦めなさい」と言われて、4歳なりに腑に落ちたんです。母にはそうやって接するものと体で覚えて。そして亡くなって、本を書いていたら涙がフワーッと出てきて、「えっ、あたし今泣いてる?」と驚いた。ああ、溜めていた涙なんだ、娘が母親の前で流したかった涙だって思いました。ビニール袋に針で穴開けたみたいに出てきた涙。「もう、泣いていいんだよ」と誰かに言われたみたいでしたね。
――この流れだとメイコさんっていかにも芸能人ズレしていて、女優然とした人間に思う人もいるかもしれないけど、メイコさんのピュアであったかい部分が本にはたくさん描かれていて、はづきさんのメイコさんに対する愛が通底している。だから支持されているのだと感じます。
はづき 私の子どもや孫が、いつかこれを読んだとき「こんなおばあちゃんだったんだ、面白いね」と思ってほしくて書きました。はじめの部分で「母へのレクイエム」と書いたのは、「そんな理由で書いてるあたしって偉くない? いい娘じゃない?」って思いから。母は非常にいい人なんです。裏表がないし、嘘をつかない。愚痴もまったく言わないし、常にポジティブ。世間一般的な「母親」としてはともかく、ちゃんと人間としての生き様を見せてくれました。
――それが結果的に、はづきさんの人生の手本になったんですか。
はづき 人生の手本というか……反面教師(笑)? ママがあんなだから私はしっかりしなくちゃ、とも思えましたから。あ、そしてこの本はね、いま子育てで大変な人に「そんな立派に母親やる必要ないよ、自分がちゃんと生きてれば子どもなんて育つから!」と伝えられたら、って思いもあるんです。私もそうだったけど、母親になると自分はそんなに立派な人間じゃないのに、立派なことを言ってしまったりする(※はづきさんは一男一女の母親)。でも子どもってそういうの、見抜くじゃないですか。
「母はその日の気分で山岡久乃風だの池内淳子風だのいろんな母親を演ってはみたものの、結局いつも中村メイコだった。中村メイコが母だったのだ」(『ママはいつもつけまつげ』81ページ)
芸能界ってものを特別視していないんですね

――この本は、神津はづきというひとりの人間の自叙伝でもある。幼少期から美空ひばりや森繁久彌といったビッグネームがそばにいるのが「普通」だった環境に、やっぱり驚きます。

はづき だから芸能界ってものを特別視していないんですね。ひばりさんみたいな人がお化粧もしないでうちに来て、「ごはんない? おかずはお漬物でいいわ」なんて言ってたり、高倉健さんにばったり会ったり。「うわあッ!」って芸能人に対して思わなくなってる。10歳の頃、初めて好きになった郷ひろみさんに会わせてもらえたときは心臓が飛び出しそうだったけれど、それぐらいですかねえ。
――あの……さっきからメイコさん、そしてひばりさんのお話のところ、本人の声色でやってくださるのがものすごく似てます(笑)。

はづき 母は誰かの話の部分はすべてその人の声色で話すので、そうやって喋るものだと思って育ったんです。母は「きょうひばりさんに会ったらさ、『ねえメイコ、あんたさあ……』って、そこに森繁のパパが来たのよ、『おおメイコじゃないか』って、さらに雪村いづみちゃんも来て『にぇ、メイコぉ?』って」、こんな感じ。私がやるとダメ出しもするし。
――モノマネのうまさって遺伝するんですね、はづきさんすごい(笑)。著名人が周囲にいっぱいいて、きっとみんなに可愛がられて育ったと思います。そういうのって、わがままな性格になる可能性もあると思うけど、はづきさんは一切そういう感じがない。
はづき もし私が美人に生まれてたら、すごくヤな女になってたと思います(笑)。そう考えると、小さいうちに「あなたはお姫さまでもないし、美人でもない」と母に言われてよかったと思って。
――本に書かれていますね。ごく小さい頃、お宅でパーティをするときに言われて、座ってないでお手伝いなさいと。
はづき 母は小さい頃、「あなたの顔は喜劇に向いてる」と言われて育ち、座右の銘も「人生は喜劇的でありたい」というような人でした。私にもなるべく早く、錯覚する前に伝えておかなきゃ、と思ったんじゃないでしょうか。
はづきさんがメイコさんにそう言われたのは、60年近く昔のこと。いまならルッキズムの観点もあってメイコさんも違った考え方をしたかもしれない。当時は容貌の話をとにかく今とはまったく違う感覚でしていた時代だった。このあたりはそういうことも含みつつ、読んでほしい。
はづき そう、本当に感覚って変わりますね。うちの親はすごく家族を表に出したがった。
――あの頃、有名人の子どもが週刊誌にもテレビにもよく出ていましたね。私も神津ファミリーが歌を披露してた番組、覚えてます。
はづき 今は芸能人の子どもの顔にモザイクをかける時代だから隔世の感ですね。私、知らない人から「あなたの小さい頃はこうだったわね」「生まれたときこんなことがあったんでしょう」と言われることがよくあって、私の知らない私のことを知ってる人がたくさんいて、いつしか慣れてしまった。「そんな生活イヤ」とも次第に思わなくなっていったんです。
超えられるわけないのに、母と同業を選んでしまいました
――高校を卒業されて、お父さま(※作曲家の神津善行氏)の教育方針でニューヨークに留学される。本にも多く書かれていましたが、海外生活は開放感があったのでは。

はづき 知らない人しかいないというのは、やっぱりラクでした。ニューヨーク大学の附属語学学校に行って、演劇クラスの聴講生になって。当時はね、マリファナ吸うような人がよくいる時代だったんですよ。1980年に行ったんですが、映画の「スーパーマンⅡ」が公開されて、クスリやって自分がスーパーマンだと錯覚してビルから飛んじゃった人が3人いたんです。「しっかりしないと」と思いますよね、夜遊びもしたけど、常に緊張感がありました。
――先ほどの反面教師もそうでしたが、状況がまずい感じだと気を引き締めてかかるというのが習性になったのでしょうかね。80年代前半のニューヨーク、治安は今より悪かったけれど、芸能やアートも元気な時代で面白そうですね。
はづき 楽しかったですよ、街角でダスティン・ホフマンを見かけたことも。カッコよかった! あるとき私、Tシャツを日本に送るアルバイトなんかしてて、大きな荷物持って歩いてたんです。そしたら手助けしてくれたのが、ロバート・デ・ニーロ。
――えええ!
はづき 「Are you Robert De Niro?」って聞いちゃいました(笑)。ちょうど「レイジング・ブル」が公開された頃でしたね。

――その辺の話もっと聞きたいけど、先へ行かないと(笑)。帰国されて1983年には俳優としてデビューされます。芸能界で親と同じ仕事をする大変さも書かれていて、痛切に感じました。七光りって、光ゆえに影もあるのだなと。
はづき ふふふ、超えられるわけないのに、同業を選んでしまいました。たまに「中村小メイコ」とも呼ばれますけど、やっぱり母の「普通じゃない部分」を見て育ってると、私は「普通」になっちゃう。芸能人として、俳優としては、それだとね……。
でも久世光彦さん(※昭和・平成期の著名な演出家。プロデュースや著述など幅広く活躍)が見つけてくれて、いろんな役をくださってうれしかったですよ。ひどい役ばかりでしたけど(笑)。
松本清張さんの「坂道の家」(1991年)では小間物屋の店員でね、久世さんが「はづき! 鏡を見て、指で鼻の横のにきびを潰して白いのブチュッと出せ」なんていきなり注文してくる。樋口一葉の「にごりえ」(1993年)では女郎の役で「お女郎さんの格好ができる!」とうれしくて。でも現場に行ったらなぜか甚平が出てくるの。久世さんいわく、「あの頃は必ず田舎のおふくろ恋しさに来るマザコンの男がいたんだ。だからはづきは湯上がりスッピン、甚平着て白いおにぎりをいつも食ってろ!」って。ええーっと思ったけど、映像見たらリアリティあるんですよね。挙句の果てに「裏庭で行水してくれ」って。やりましたよ。そしたら「はづき、腹へこますなーッ!」って(笑)。
――「古畑任三郎」の桃井かおりさんの回とか、はづきさんが出てらしたの覚えてます。そして1992年には俳優の杉本哲太さんと結婚。メイコさんに哲太さんがお許しを得に来るところ、本の中でも面白かったなあ。
はづき はい、そしてだんだん私は「家庭内女優」にシフトして(笑)。
――今回のエッセイ、読み終えてまず思ったのが「書き切れなかったエピソード、まだたくさんあるのでは」ということでした。今後も書きたい、という思いはありますか。
はづき 60歳を超えて、今後やれることにも限りが見えてきました。その中では「書くこと」って思いを研ぎすますのにすごくいいし、書きたいなと思います。書けるかな……とも思うけど、ポジティブですからね。そこは毛穴から母に学んできた(笑)。母だって大変なこともあったけど、「あったわねェ、そんなことも!」ってすべて笑い話にしちゃう。そういうのを見てるうちに、「まあ、いっか」って思えるようになっていったんだなとあらためて思います。

神津はづき(こうづ・はづき)
1962年8月(つまり、葉月)、東京都生まれ。俳優として1983年にデビュー。現在は刺繍作家としても活動、不定期に教室を開催中。また受注ブランド「Petit tailor R-60」も展開、自身の年代の女性が着やすく素敵に見える洋服を製作し、こちらも好評を得ている。
instagram:@hazukitoito
聞き手・構成 白央篤司(はくおう・あつし)
フードライター、コラムニスト。「暮らしと食」をメインテーマに執筆する。主な著作に「にっぽんのおにぎり」(理論社)、「自炊力」(光文社新書)、「はじめての胃もたれ」(太田出版)などがある。
https://note.com/hakuo416/n/n77eec2eecddd
ママはいつもつけまつげ: 母・中村メイコとドタバタ喜劇

定価 1,870円(税込)
小学館
この書籍を購入する(Amazonへリンク)
文=白央篤司
撮影=佐藤 亘
あわせて読みたい
-

- 暮らし、遊び、乗り物の総合展示会「FIELDSTYLE JAPAN 2025」がアジア最大級のスケールで開催!
- 毎回大盛況の「FIELDSTYLE」が、今年もやって来る!2025年5月17日(土)・18日(日)に、「AICHI SKY EXPO(愛…
- (Walkerplus)[健康食材,芸術]
-

- 【介護のピンチ、解決します!】これまでのやり方を変えないのが大事? 新生活に戸惑ったら
- 正解はないけれどこのやり方はおすすめできないと思うことはあるのです / (C)稲葉 耕太(くろまめさん)…
- (レタスクラブニュース)[田舎暮らし]
-

- ANAインターコンチのアトリウムラウンジでハーブのアフタヌーンティー
- ANAインターコンチネンタルホテル東京(港区赤坂1、TEL 03-3505-1111)内の「アトリウムラウンジ」が5月1…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東京都]
-

- 全てを知った上での求婚だった? 結婚を申し込んだその理由/現代OLが18世紀フランスにタイムスリップしたら(11)
- 全てを知っていての提案 / (C)みやのはる、堀江宏樹/KADOKAWAホテルを抜けた先にあったのは、18世紀の…
- (レタスクラブニュース)[メイク]
-

- 5月12日の月が教えてくれるヒント 夜に散歩する
- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと1日。 満月前日。月は蠍座で満月に…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.