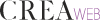なぜ彼は弔辞の代筆をしているのか? 夢破れた脚本家が見出した、新たな物語の作り方
日々激変する世界のなかで、わたしたちは今、どう生きていくのか。どんな生き方がありうるのか。映画ライターの月永理絵さんが、映画のなかで生きる人々を通じて、さまざまに変化していくわたしたちの「生き方」を見つめていきます。
今回は、4月25日から全国公開中の映画『来し方 行く末』に注目。
あらすじ
北京の大学院で脚本作りを学んだウェン・シャンは、思うように仕事を得られず、今は葬式で読まれる弔辞の代筆業をして生計を立てていた。同居人のシャオインと暮らしながら、依頼主から話を聞いては、亡くなった人たちの人生を美しい物語にまとめ上げる。その丁寧な仕事ぶりが評判を呼び、次々に仕事が舞い込むが、彼自身は今の生活に行き詰まりを感じ始めていた。リウ・ジアイン監督作品、主演は『チィファの手紙』『鵞鳥湖の夜』などで知られるフー・ゴー。
人生を「美しい物語」にまとめることはできるのか?

彼はいつも耳を澄ませている。彼の仕事は、依頼を受け、誰かの人生を文章としてまとめあげること。そのためには、たくさんの人々に取材をし、対象となる人の人生を誰よりも詳しく知らなければいけない。その人は、どんなふうに生きたのか。誰と出会い、どんな交流をした人なのか。どんな性格で、何を生業にしていたのか。とりとめなく語られる話に耳を傾け、口が重い相手にはそれとなく質問を重ね、ひたすら人の話を聞き出していくのが彼の役目だ。ただし、肝心の本人に話を聞くことはできない。なぜなら、彼が書くのは、その人の葬式で読まれる弔辞の文章だから。

遺族ではなく、プロが弔辞を代筆するのが北京では実際に流行っているのだろうか。わからないが、少なくとも映画のなかの世界では、主人公ウェンが行う弔辞の代筆業は、忙しい現代人に向けた新たなビジネスとして人気を博しているらしい。とはいえ、それは彼が本来望んだ仕事ではない。脚本家を目指していたウェンにとっては、いわば食い扶持を稼ぐための仕事のはずだった。だが気づけば脚本が書けないまま中年になり、かつての同級生はすでにドラマや映画の分野で活躍している。田舎にいる家族には、脚本家として働いていると嘘をついたまま。このままでいいのか、一念発起して脚本を書き上げる日は来るのか、同居人のシャオインにもせっつかれ、ウェンの心は迷い始める。

そんな逡巡があるせいか、映画の中のウェンはいつも不安げに見える。根源にあるのは、自分が本当に人の話を聞けているのか、という不安と自信の無さ。取材はこれで十分だったのか。何か大事なものを取りこぼしてしまったかもしれない、という不安が最後まで消えず、彼は何度も原稿を書き直す。そもそも何十年と生きた誰かの人生を、ひとつの美しい物語にまとめるなんて不可能だ。本人亡き今、すべての過去を知ることはできないし、息子から見た父の顔と、娘から見たそれとがまったく別のものであるように、視点によって見え方はがらりと変わる。たとえ本人の声が聞けたとしても、それが真実とは限らない。誰かの人生を物語るとは、なんて難しく厄介なことだろう。
生活の細部に目を凝らすこと

面白いことに、ウェンはただ周囲にいた人々に話を聞くだけでなく、必ず亡くなった人がかつていた場所を訪れる。その人が暮らした場所で、その人が座ったのと同じ場所に座ってみる。生前に囲まれていた音の中に身を置き、かつて見たはずの景色を眺める。苦労して火鍋屋を立ち上げた男の弔辞を書く際には、彼が経営していた店まで行き、従業員たちの仕事ぶりを眺め、店に集まる常連客の喧騒に耳をすませる。急逝したIT企業の社長が仲間たちと働いてきたオフィスに行き、故人が愛用したフィットネスバイクを漕いでみたりもする。依頼主の中には、自分の死後の弔辞を予約している女性もいて、ウェンはたびたび彼女の家を訪ねては、今の生活そのものに目を凝らす。

弔辞を書くためにここまでする人は、ウェン以外には普通いないはずで、ただ話を聞いて原稿を書くだけではだめなのかと驚く依頼主も多い。ウェン自身、どこまで自覚的にそうしているのかはわからない。遺族や友人たちの話を聞くために訪れた場所で、ふとその場の空気に触れてみたくなった、その程度のことかもしれない。けれど、その人がいた場所に自分の身を置くことで、彼女/彼がどのような生活をしていたのかをたしかに感じ取ろうとする、ウェンの振る舞いのひとつひとつにぐっと心を掴まれた。

そしてそれは、この映画の姿勢そのものでもある。ウェン・シンとはどういう人なのかを語ろうとすると、いくつかの言葉がパッと浮かぶ。夢に破れて挫折した脚本家。中年の危機を迎えた人。都会の片隅で寂しく暮らす孤独な男。わかりやすい肩書ならいくらでも挙げられるけれど、彼という人間の本質は、そんな言葉では掴みきれない。それよりも、彼がどんな家でどんなふうに毎日を過ごしているか。食事や家事の仕方。部屋に差し込む光の変化や、自転車で移動するときの風の受け方。仕事の息抜きにいつも出かける場所や、そこで見た景色。家の外にやってくる猫との交流。そうした画面に映るすべての些細な事柄によって、ウェン・シンというひとりの人物が、私たちの前に少しずつ浮かび上がる。この映画は、その過程を何より大事にしているのが、よくわかる。
物語を書くとは、大きな出来事や個性的で面白いキャラクターを作り上げることに限らない。生活の細部、ひとつひとつに目を凝らし、耳を澄ませ、それらをたしかに描写すること。そこから物語が生まれていく。そして人生もまた、そんなふうにつくられる。
文=月永理絵
あわせて読みたい
-

- 教授に結婚報告へ。「結婚するヒマあったんだな」いやいや全然ヒマなんてないです
- 結婚します / (C)さーたり/KADOKAWA属性過多なアメブロトップブロガー・さーたりの原点ここにあり!?オ…
- (レタスクラブニュース)[田舎暮らし]
-

- 細部までこだわった内部設計で高音質を実現!天然木の質感も魅力的な【ジェイブイシーケンウッド】のスピーカーがAmazonで販売中‼
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[動物]
-

- CREA表紙プレイバック【1994年10月号〜12月号】たのしい文学、アジアが興奮!、マジメなお仕事、アブナイお仕事
- 創刊まもない頃の表紙に並ぶのは、ニュースな話題。CREAが創刊した1989年は、世界史的に見ても、エポック…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
-

- 東浦和の画廊「ギャラリーペピン」で10周年記念企画展
- ギャラリーペピン(さいたま市緑区大牧)の10周年記念企画展「Gallery Pepin 10th Anniversary 一条美由紀…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ESG]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.