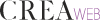「最初の15秒が勝負」「オンオフを分けない」本が売れない時代に50万部売る! 書籍PRの“おきて破り”の非効率仕事術

「効率化」が正義とされるこの時代に、“あえて非効率”を貫くPRパーソンがいます。それが書籍PRの黒田剛さん、その人です。
『妻のトリセツ』や『続・窓ぎわのトットちゃん』(ともに講談社刊)など数々のベストセラーを手掛け、なかには50万部を超えるヒットを記録した書籍も。「1万人に広く伝える」よりまず「1人に深く伝える」を重視する黒田さんの仕事術は、合理化とは対極にあるように見えて、実は誰よりも本質的で戦略的です。
関係性を丁寧に育て、“人に選ばれる”ための「非効率」の哲学について、お話を伺いました。
非効率は「人と人の関係」を耕す手段

――書籍PRという仕事の中で、“非効率”を大切にされているのは意外でした。
黒田 自分では「効率悪い」とは思っていないんですけどね。僕が大事にしているのは、「人と人の関係」なんです。メール1通にしても、定型文では送らずに、相手に合わせた一言を添えるようにする。自分が参加する必要のない取材や打ち合わせにも立ち会う。そうやって、「この人と仕事したい」と思ってもらえる関係を作っていく。そんなふうに仕事をしていることが、人からは非効率に見えるみたいで。こうすることが結果を生んでいるので、自分としては効率がいいつもりなんです。
――その積み重ねが、ベストセラーを生んでいるんですね。
黒田 そうだとしたらうれしいです。実際、PRって話術や資料の作り方だけじゃないと思うんですよ。“人として付き合いたいかどうか”が、すごく大きい。だから僕は、仕事でもプライベートでも、人との距離の取り方をあまり変えてないんです。

――仕事とプライベートを切り分けないという考え方は、正直、なかなかハードルが高いように感じます。
黒田 僕も昔は「オンオフをしっかり分けなきゃ」と思ってたんです。でも、ある時、プライベートで絶対に言わないようなことを、仕事だからって言っている自分に違和感があって。そこからは、「全部、人と人の関係なんだから、無理に分けなくていいじゃん」って思うようになりました。
――相手と誠実に関わる姿勢があるからこそ、自然と関係が築かれていくんですね。
黒田 そうですね。自分がされて嫌なことは相手にもやらないし、嬉しかったことはちゃんと伝える。これって小学校で教わるようなことかもしれませんが、僕はどんな相手でも“人と人”として接したいんです。
――嬉しかったこともちゃんと伝える。大事なことだけれど、意識しないとできていないかもしれません。
黒田 自分の中で決めているのは、思ったときにすぐ言うことですね。後で言おうと思っても忘れるし、伝え方もぎこちなくなるので(笑)。だから、「◯◯さんとお会いできて嬉しいです」とか、「◯◯をしてくださって、嬉しかったです」とか。自分なんかが伝えなくてもいいかもと躊躇してしまいがちですが、まずは自分から心を開くようにしています。
“15秒”でつかみ、「ちなみに」で印象を残す

――PRの現場で大切にしていることは何ですか?
黒田 「最初の15秒」が勝負だと思ってます。書店員さんやテレビ関係者をはじめとしたメディアの方って、毎日膨大な情報にさらされているから、最初の一言で心をつかまないと埋もれてしまうんですよ。
――確かに、最初で惹かれなければ、心は離れてしまいますよね。
黒田 そうなんです。たとえば、「○○というお店のシェフが書いた料理の本なんですけれど……」と話したあとに「実はブルーノ・マーズが日本で最初に訪れたらしいですよ」と付け加えるよりも、最初から「ブルーノ・マーズが日本で最初に訪れたレストランのシェフが書いた本です!」という伝え方ができると、興味を持ってもらえる確率は一気に上がる。情報の切り取り方と順番って、実はものすごく大事なんです。
――なるほど……! 本には、小さい頃から夕食のテーブルで家族にその日の出来事を面白おかしく話していたというエピソードがありましたが、話術が鍛えられていたんですね。
黒田 そしてもう1つ大切なのが「ちなみに」のひと言です。「ちなみに、この著者は毎回靴下がかわいいんですよ」とか、「毎朝5時に畑に行ってから原稿を書いているらしいです」とか、本題とは関係ない話のほうが記憶に残るんですよね。情報より“人”の気配がある方が心に残るというか。
――その人らしさが垣間見える情報って、誰かに話したくなります。
黒田 そうでしょう(笑)? 僕はそれを「デザートの一言」って呼んでます。メインはちゃんと伝えるけど、最後に小さな喜びを残すと、ぐっと印象が深まるんですよ。
みんなのハッピーを探す。だから信頼される

――対人関係では「言うべきか迷う」場面もあると思いますが、黒田さんはどうされていますか?
黒田 違和感があるときにはしっかり伝えますね。うやむやにしないことは、人間関係を構築するうえで大事なことだと思うんですよね。違うと思ったら、相手が誰であってもちゃんと伝える。メディアに求められたとしても、著者さんがイヤがることがあったら、「これはできません」と必ず伝えます。
――ちゃんと伝えるからこそ、信頼につながるんでしょうか。
黒田 そう思います。ただ、僕が大切にしているのは、「自分が言いたいことを言う」ということではないんです。メディア、著者、編集者……誰か一人でもイやな気持ちになる人がいないように、関わっているすべての人がハッピーになる道を探すようにします。
――信頼を築けても、提案が断られることってありますか?
黒田 もちろんです。でも、そこで終わりにしないんです。「どこがダメだったのか」「どこが良かったのか」を相手に聞くようにしてるんです。それが次の提案を強くしてくれるので。
それでブラッシュアップして磨きをかけていくと、その提案が決まったりします。そうしたら、アドバイスをくれた人に「〇〇さんのアドバイスのおかげです!」と必ずお礼を伝えます。そうすると、相手も喜んでくれるし、人との縁がまたつながるんです。
AIは便利な相棒。でも最後に決めるのは自分

――最近はAIを使って業務を効率良くする人も増えていますが、黒田さんはどう取り入れていますか?
黒田 全然使ってますよ。文章の校正したり、辞書代わりにリサーチしたり。でも、出てきた情報の良し悪しを判断するのは、結局人間の目なんですよね。
――内容の正確さだけじゃなく、「この言葉は相手に響くか?」みたいな感覚は、AIには難しい部分ですよね。
黒田 「この一言で心が動くか」っていうのは、数値化できない。だからこそ、判断をAIに丸投げしちゃダメだと思っていて。僕はよく「AIは、料理まではしてくれるけど味見するのは自分」って言ってるんです。
――すごくいい表現ですね。AIを使いこなすにも、人間側の「目利き力」が必要だと。
黒田 まさにそうです。便利なツールほど、使う側の力量が問われる。だからAIを導入すればするほど、自分自身の「判断する力」が鈍らないように意識してます。最終的に信用されるのは、誰がその言葉を選んだかなんですよ。
だから、ラクをするためにAIを使うというより、人にしかできない判断の質を上げるために使う。そしてその判断って、ちょっと遠回りだったり、余白を残したりする非効率の中から生まれることも多いんです。AIとどう付き合うかにも、人とどう向き合うかと同じくらい、丁寧さがいるんじゃないかと思っています。
黒田剛(くろだ・ごう)
書籍PR/非効率家。株式会社QUESTO代表。1975年、千葉県で「黒田書店」を営む両親のもとに生まれる。須原屋書店学校、芳林堂書店外商部を経て、2007年より講談社にてPRを担当する。2017年に独立し、PR会社「株式会社QUESTO」を設立。講談社の『妻のトリセツ』(黒川伊保子)は、シリーズ70万部を超えるヒットを記録。『いつでも君のそばにいる』(リト@葉っぱ切り絵)をはじめとする葉っぱ切り絵シリーズは30万部を突破。『続 窓ぎわのトットちゃん』(黒柳徹子)は、発売2ヵ月で50万部突破。その他、KADOKAWA、マガジンハウス、主婦の友社、岩崎書店など、多くの出版社にてPRを担当。非効率ながらも成果を出す独自の仕事術をセミナーなどを通して伝えている。

非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方
定価 1,760円(税込)
講談社
文=船橋麻貴
写真=橋本 篤
あわせて読みたい
-

- スワロフスキー入りリング? いえ、ワイヤレスイヤホン「Moto Buds Loop」です
- スワロフスキー入りリング? いえ、ワイヤレスイヤホン「Moto Buds Loop」ですImage: Raymond Wong - Gizm…
- (Gizmodo Japan)[カフェ・スイーツ]
-

- 【5月5日~5月11日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い<全体運・金運・ラッキー食材>
- 今週の運勢をチェック!ラッキー食材もお伝えします今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運…
- (レタスクラブニュース)[自然化粧品,レシピ]
-

- 荷物が多くても安心の収納設計!【ニューバランス】のトップローディングタイプリュックが今ならAmazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[日常のスポーツ,アウトドアファッション]
-

- シンプルで洗練された一枚が春コーデを格上げ!【ザノースフェイス】の高機能コーチジャケットがAmazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[アウトドアグッズ]
-

- カリスマ書籍PR・黒田剛さんの“非効率”な仕事を支える〈働くのがもっと楽しくなる〉極上映画7選
- ゴールデンウィークに制覇したい! 大型連休でほっとしている人、連休明けからもっとがんばろう! と張り…
- (CREA WEB)[千葉県,CREA WEB]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.