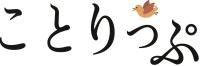【招待券プレゼント】京都で巳年にちなんだ新年の幸せ祈願、博物館でのアート始めも♪

新しく迎える2025年は巳年。ヘビは、古くからその強い生命力にあやかり、病気を治してくれる力があると信じられてきた存在です。また、七福神のひとり、弁財天のお使いという顔も。そんな特別な力をもつヘビの姿を、昔の人は絵画や工芸品に表してきました。このお正月は、干支にちなんだヘビに出会える社寺やミュージアムをめぐってみませんか?
さらに、今回は京都国立博物館で開催の新春特別展「巳づくし ―干支を愛でる―」の招待券を、ことりっぷweb読者のみなさまの中から抽選で5組10名様にプレゼントします。
大豊神社へは、市バス宮ノ前町で下車。徒歩で2~3分の哲学の道から長い参道に誘われて進むと、やがて鳥居が現れます。社殿の背後の山は椿ヶ峰と呼ばれ、冬から春にかけて、さまざまな種類の椿が花を咲かせるそう。
平安時代に宇多天皇の病気平癒を願い創建された大豊神社には、医薬の神様である少彦名命(すくなひこなのみこと)が祀られています。
ヘビはその強い生命力と、脱皮をすることで蘇りや若返りの象徴とされ、医療とつながりが深いことから、本殿前に狛巳(へび)が鎮座しているそうです。また、水の神様でもあり稲作を左右したことから、転じて蓄財や金運の御利益もあるのだとか。
境内には、狛巳のほかにも、狛ねずみ、狛猿、狛鳶、狛狐の愛嬌のある姿も見られますよ。
出町妙音堂へは、市バス河原町今出川、または京阪出町柳駅から徒歩で2~3分の賀茂川にかかる出町橋へ。橋の西詰にそっとたたずむ石の鳥居をくぐって、弁財天が祀られている妙音堂に向かいます。
寺は、鎌倉時代に、後伏見天皇に嫁いだ西園寺寧子が持参した青龍妙音弁財天画像を祀ったことに始まります。明治時代には伏見宮家とともに東京へ遷りましたが、地元の強い願いから現在地に妙音堂を建立。今も「出町の弁天さん」と親しまれています。
七福神の紅一点、芸術、特に音楽を司る弁財天は、もともとはインドで川の神様とされていました。そう考えると、琵琶が家業でもあった西園寺家ゆかりの妙音堂が、賀茂川のそばにあるのも納得です。
その弁財天のお使いが白蛇ということから、妙音堂の壁には数枚の蛇の絵馬(額)が奉納されています。技芸上達や福徳円満のご利益があるそうなので、お稽古事のスキルアップもお願いできそうです。
京都国立博物館へは、市バス博物館三十三間堂前下車すぐ、または京阪七条駅から徒歩7分でアクセスできます。
博物館は明治時代に開館し、平安時代から江戸時代にかけての京都の文化財を中心に収蔵しています。広々とした庭園で迎えてくれるのは、開館当時の赤レンガ建築「明治古都館」と、対照的なモダン建築「平成知新館」。
平成知新館で開催される、新春の特集展示「巳づくし ―干支を愛でる―」は、縄文時代の土器から江戸時代の絵画や工芸まで、ヘビがテーマの展覧会。
昔の人は、細長い体の不思議な生き物を見て、恐ろしく思いながらも、特別な存在だと考えてきたようです。不気味? かっこいい? それとも、かわいく感じるでしょうか?
ことりっぷweb読者のみなさまの中から抽選で、1月2日から京都国立博物館にて開催される「巳づくし ―干支を愛でる―」の招待券を5組10名様にプレゼントします。 ことりっぷWEB・アプリ会員の方は当選確率が2倍になるので、ぜひ会員登録を行った上で応募してくださいね。
会期 :2025年1月2日(木)~2月2日(日)
会場 :平成知新館
○応募締切:1月5日(日)
○発送時期:1月10日(金)頃
干支の「巳」をテーマにした初詣や、アート始めはいかがでしたか? ちょっぴり怖くて、不気味というヘビのイメージが一転するかもしれませんね。このお正月は、大豊神社や出町妙音堂にお参りして、ご利益をたっぷりいただきましょう。
あわせて読みたい
-

- 伊勢神宮、式年遷宮最初の祭典「山口祭」「木本祭」 伐採と搬出の安全祈願
- 伊勢神宮の社殿や神宝などを20年に1度新しくし、ご神体を新宮(にいみや)に移す式年遷宮の最初の祭典に当…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[まち歩き]
-

- 墨田・京島で「刑務所アート展」 受刑者の表現、壁越えた対話に
- 受刑者が制作した絵画や詩、手紙などを展示する「第3回刑務所アート展」が5月24日、京島劇場(墨田区京島3…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術]
-

- 「夫との旅行はムリ!」“店構えでおいしいか分かる”と言い張る夫と2時間歩いた後の悲劇
- ゴールデンウイークを控え、旅行の計画を立てている人も多いだろう。だが、中には日常生活では問題がなく…
- (All About)[正月]
-

- 代官山で100種類以上の“プチストレス”に共感しちゃう!?新感覚イベント、ミンティア「日常のなんてこった書店」が登場
- アサヒグループ食品株式会社は、「日常のなんてこった書店 Presented by MINTIA」を2025年4月24日から5月1…
- (Walkerplus)[東京都]
-

- まるでフランスへ旅をする気分 ♪ 京都・西陣「cafe cirque」できらめくミニタルトを
- 京都の西陣織が生まれる町として知られ、かつては機織りの音が響いていた西陣エリア。いくつもの京町家が…
- (ことりっぷ)[ことりっぷ]
キーワードからさがす
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.