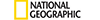【動画】チンパンジーのドラムと「言葉」にヒトと似た特徴、研究

チンパンジーはリズミカルに木の根を叩き(ドラミング)、そのスタイルは集団によって異なるという発見が、2025年5月9日付けで学術誌「Current Biology」に報告された。観察によれば、ドラミングは群れの他のメンバーと情報を共有する手段であることが示唆される。リズミカルな打撃音に基づくユニークなコミュニケーション方法だ。この能力はヒトとチンパンジーの共通祖先から生じた可能性があると、科学者たちは考えている。
「彼らが木の根を強く叩くと、体に響いてきます。信じられないほど印象的です」と、論文の筆頭著者であるベスタ・エレウテリ氏は語る。
エレウテリ氏はオーストリア、ウィーン大学の認知生物学者で、チンパンジーのドラミングを研究しており、アフリカ5カ国で350回以上のドラミングを観察した。
西アフリカのチンパンジーは、手で木につかまりながら足で木の根を蹴り、時には800メートル以上も離れた場所にまで届く力強い音を出す。
「時には非常に速く、手足がぶれて見えるほどです」と、この研究に関わった英セントアンドリュース大学の霊長類学者キャサリン・ホベイター氏は言う。「チンパンジーは熱帯雨林の巨大な木の板根(ばんこん、地面より上に伸びる大きくて広い根)の間を飛び移り、まるで踊るように手足で木を叩くのです。本当に驚くべき光景です」
一部同じチンパンジーを対象とした別の新たな研究は、チンパンジーが声を組み合わせて複雑な意味を伝えていることを発見した。これは、動物のコミュニケーションと人間の言語の間をつなぐ足がかりとなる可能性がある。論文は2025年5月9日付けで学術誌「Science Advances」に掲載された。
これらのチンパンジーの行動を観察することで、人間の音楽や言語がどのようにして始まったのかを知る手がかりが得られるかもしれない。
「現代の音楽を作るために私たちが使ってきたようなものの構成要素が、ヒトがヒトになるずっと前から存在していたことがわかります」と、ホベイター氏は言う。
次ページ:チンパンジーのドラミングと鳴き声のどこが特別なのか
チンパンジーのドラミングと鳴き声のどこが特別なのか
リズミカルな音楽をつくるのは長い間、ヒト特有の能力だと考えられてきた。打楽器演奏はヒトの音楽表現の最も初期の形の一つだ。ドラミングには個人差や地域差があるが、一般的にはランダムではないタイミングで構成される。つまり、打撃は均等な間隔で行われ、一定のリズムになる。この特徴が今回のチンパンジーでも見られた。
エレウテリ氏とホベイター氏の2022年の研究は、チンパンジーが板根を叩いて、遠くと近くに情報を送っていることを発見した。チンパンジーはそれぞれ独自のドラミングスタイルを持ち、森の中のどこにいて何をしているのかを共有するために、ドラミングと「パント・フート」と呼ばれる鳴き声を組み合わせる。
すべての動物がコミュニケーションをとるが、ヒトは地球上で言語を使用することが知られている唯一の種だと考えられている。言語とは、音を単語に、単語を文に組み合わせて意味を作り出すことを指す。
鳥などの他の動物はメッセージを送るために発声する。これらの鳴き声を組み合わせる種もいるが、この行動は通常、数種類の鳴き声に限られ、捕食者の存在を他の個体に知らせるという状況に限定される。
チンパンジーとヒトに近縁なボノボも複雑な組み合わせを使用する。そのため、霊長類学者は、ヒトの言語の謎めいた起源は、700万〜500万年前の3種すべての共通祖先に由来するのではないかと考えている。
「Current Biology」に掲載されたドラミングの研究では、コートジボワール、ギニア、セネガル、ウガンダ、タンザニアの11のチンパンジーのコミュニティーにおける371回のドラミングが分析された。
「最近まで、ヒトの音楽リズムに類似した霊長類のリズミカルな行動に関する説得力のある証拠はあまりありませんでした」と、ノルウェーのオスロ大学の言語学者で、テナガザルのリズミカルな踊りを研究しているプリティ・パテル・グロシュ氏は、メールで述べている。「チンパンジーが木の板根を叩く行動が人間の音楽行動の特徴を示すという観察は、大発見です」。なお、氏は今回の研究には関与していない。
コートジボワールでドラミングするチンパンジーを研究しているプロジェクトは、上記の研究だけでなく、「Science Advances」に掲載された研究にも貢献した。こちらでは、53頭のチンパンジーから録音された4000以上の音声を分析し、チンパンジーがどのように発声を組み合わせているかを探った。
鳴き声は、採餌、巣作り、接近、攻撃、あるいは捕食者との遭遇といった特定の出来事に関連していた。2つの鳴き声を組み合わせることで、単純な鳴き声よりも多くの意味を伝えており、日常のさまざまな活動に及んでいた。
例えば、「フー」という鳴き声は通常、採餌や移動中に使用され、「パント」と呼ばれる鳴き声は主に他のチンパンジーとの社会活動中に使用された。しかし、「フー」と「パント」を組み合わせた鳴き声は巣作り中に使用され、完全に新たな意味を生み出していた。
次ページ:リズムと言語の進化
「このシステムが多機能であることは予想していましたが、我々の予想をはるかに超えていました」と、フランス国立科学研究センター(CNRS)の進化生物学者で研究著者のセドリック・ジラール・ブトス氏は語る。「このシステムには、私たちが言語に見出す言語現象のほとんどが含まれています」
複雑なチンパンジーの発声は、動物の単純な鳴き声と、長さに制約のないヒトの言語の間をつなぐ進化の架け橋になる可能性があるとジラール・ブトス氏は言う。
「チンパンジーのコミュニケーションには、ヒトのようなシステムの萌芽が組み込まれているのかもしれません」とパテル・グロシュ氏は今回の発見についてメールに書いている。
リズムと言語の進化
「人間の認知において、言語と音楽は密接に関連しており、同じ認知資源を共有している可能性があると、多くの学者が主張してきました」とパテル・グロシュ氏は書いている。例えば、2014年8月5日付けで学術誌「Psychonomic Bulletin & Review」に掲載された研究では、言語と音楽を脳の同じ部分を使って処理することが示されている。
氏は、さらなる研究によってこの関連性をより明確にできると提案する。「つまり、チンパンジーの音声コミュニケーションとリズミカルなドラミングは共に進化したのでしょうか? このことは言語と音楽の進化に関する私たちの理解に役立つのでしょうか?」
「ヒトの言語の進化を調べる場合、私たちは通常、動物の音声コミュニケーションと比較します」と、フランス、レンヌ大学の進化生物学者マエル・ルルー氏は説明する。「ヒトの言語は音声だけではなく、音とジェスチャーを組み合わせたマルチモーダルな(複数の形式を使う)ものです」
これは、ヒトの言語の起源もマルチモーダルであることを示唆しているとルルー氏は言う。なお、氏は今回の研究には関与していない。
研究者が調査した範囲では、コミュニティーごとに異なるドラミングスタイルが観察されたが、これはヒトの言語の多様性も反映しているのかもしれないとルルー氏は語る。
ニシチンパンジー(Pan troglodytes verus)は通常、比較的頻繁に速くドラミングするのに対し、ヒガシチンパンジー(Pan troglodytes schweinfurthii)はゆっくりとドラミングし、鳴き声の中でドラミングを始めるタイミングが遅い。
ホベイター氏は、これらの違いは東部と西部の集団間で見られる異なる社会構造がつくり出したと考えている。ヒガシチンパンジーはどちらかというと攻撃的で階層的であり、ニシチンパンジーは結束力があり平等主義的だ。
氏はさらに、リズムは人間の社会性やダンス、スピーチで重要な役割を果たしているため、私たちの社会行動もリズムを発達させた方法と関連していた可能性があると指摘する。
「このような科学的な研究は、チンパンジーのどんな群れにも保全と保護をする価値があるという事実を私たちに気付かせてくれます」と、ホベイター氏は言う。「私たちは、チンパンジーがコミュニケーションやリズム、社会行動において文化をもっているかもしれないと認識し始めています。もしある集団を失えば、それに伴う独自の文化も失うことになるのです」
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社