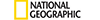手先が不器用になる子どもたち、「驚くべき異変」を専門家が危惧

エイミー・ホーンベック氏は、今の生徒たちの様子に違和感を覚えている。子どもたちは上着のファスナーを開け閉めしたり、本のページをめくったりができない。スプーンすらちゃんと持てない。こうした変化に気づいているのはホーンベック氏だけではない。米教育関連メディアのエデュケーションウイークによる2024年の調査によると、教師の77%が、低学年の子どもは5年前の同学年の子どもに比べて鉛筆やペンやハサミをうまく扱えないと報告している。また69%が、靴のひもをうまく結べない子どもが増えていると感じると回答している。
米ニュージャージー州ビバリー公立学校で教育指導を行うホーンベック氏は、たった3個の積み木を積み重ねるよう言われた子どもたちが戸惑う様子を見て、「積み木を見たことがないかのようです」と表現する。「どういう風にするかを教えたあとでも、子どもたちが取る行動には驚くばかりです」
現代の子どもたちは、重要な「微細運動能力」を失いつつある。微細運動とは、靴ひもを結ぶ、ペンで字を書く、物を積み上げるといったときに必要な、細かく正確な動きのことだ。
スクリーンタイム(画面を見ている時間)、生活習慣の変化、子ども時代の体験の変化といった要因が複雑に絡みあった結果だと専門家は指摘する。この記事では、親が知っておくべきことを紹介する。
コロナ禍の影響は?
微細運動能力の低下を新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的大流行)のせいにするのは簡単だ。
パンデミックの1年目(2020年3〜12月)に生まれた250人以上の赤ちゃんを対象にした米国での研究によると、生後6カ月での微細運動テストでは、パンデミック中に生まれた赤ちゃんは、それ以前に生まれた赤ちゃんよりも点数が低かった。
この研究を行った米ニューヨーク大学グロスマン医学部教授のローレン・シャフリー氏は、この結果が胎児期ストレスの増加によるものなのか、パンデミック中に生まれた赤ちゃんが生後間もない時期に経験した、通常と異なる環境によるものなのかを判断するのは難しいと語る。
親が共働きのなかで子どもが家にいる時間が長くなったことも、全年齢で子どものスクリーンタイムが増える要因となった。スクリーンタイムの長さは微細運動能力の発達の遅れと関連していることが、研究でわかっている。
2023年8月に医学誌「JAMA Pediatrics」に掲載された7000人以上の日本の子どもを対象とした研究では、1歳のときに画面を見る時間が1日4時間以上だった子どもは、1時間未満だった子どもに比べ、2歳のときに微細運動能力に発達の遅れがあるリスクが1.74倍になることがわかった。
次ページ:画面が手先を使う遊びを奪っている
「理想的とは言えない状況の中で、親はすべきことをしていました」とシャフリー氏は言う。
一方、米ラトガース大学全米早期教育研究所の共同所長のスティーブン・バーネット氏は、そうした傾向はパンデミック以前からあったと考える。「それまでにもずっと存在していた問題です」と氏は言い、パンデミックによって、すでにあった問題が加速したかもしれないと示唆する。
画面が手先を使う遊びを奪っている
スマートフォンやタブレット端末、電子書籍、テレビなどの画面を見ている時間は、子どもが何かを作ったり組み立てたり、絵を描いたりする時間を削る。そうした端末を使った算数の学習やデジタルアートの作成は、教育効果はあるが、書く、切る、色を塗るといった動作に伴う細かな運動能力を育てることはできない。
また、微細運動と粗大運動(全身を使った大きな動き)の能力の発達に欠かせない屋外での遊びも減っている。「子どもたちは、穴を掘る、花を摘むなど自分ひとりでも楽しめる遊びをしていません」とバーネット氏は指摘する。
子育てに便利なものが登場したことも運動能力の発達に影響を及ぼしているとホーンベック氏は言う。
ファスナーやボタンの付いていない伸縮性のあるズボンは、忙しい朝には時間の節約になる。パックに入ったおやつは散らからない。だが、こうした便利さは、ファスナーの開け閉めやボタンの留め外し、食器の扱いを練習する機会を子どもから奪っている。
ホーンベック氏によると、子どものおもちゃの好みも変化しているという。パズルや木製の積み木など、根気や正確さを必要とするおもちゃは、簡単にくっつくマグネット式のタイルに取って代わられている。
また、ホーンベック氏が観察した4クラスのうち3クラスでは、3時間の間に誰ひとり読書エリアに行こうとしなかったという。「これは非常に大きな変化です」と氏は言う。「誰も本を読みに行こうとしないなんて、過去には一度もありませんでした」
次ページ:微細運動能力を育てるには
米調査会社ピュー・リサーチ・センターのデータによると、こうした状況は、娯楽のための読書が米国の子どもたちの間で大幅に減ってきているという全般的な傾向を反映している。
本のページをめくるのは、たいした作業ではないように思えるかもしれない。だが、読書によって養われる「集中して手順に従う」というもっと幅広い能力は、上着のファスナーを開け閉めする、靴ひもを結ぶといった動きに不可欠なものだとホーンベック氏は指摘する。
読書の減少は読み書きの能力に影響するだけでなく、注意の持続時間や集中力など、微細運動能力の発達に不可欠なスキルにも波及する。「単純な作業に対するフラストレーションのレベルが実に高くなってきています」とホーンベック氏は言う。「そのため子どもはすぐ『もうやめた、もうやらない』となります」
また、バーネット氏によると、作業に対する集中力、とりわけ努力が必要な作業に対する集中力の低下は、微細運動能力の低下の大きな要因の1つだという。パズルを例に取ってみよう。パズルを完成させるには、戦略を立て、ピースの向きを変え、試行錯誤する必要がある。
しかし、ホーンベック氏は「多くの子どもは『無理』といった反応をします。コンピューターゲームでは、コンピューターがピースを回転させてくれるので、それに慣れているのです」と語る。「それに、タブレット端末は、現実世界とは比べものにならない速さで手助けしてくれますから」
微細運動能力を育てるには
ホーンベック氏は、機会を見つけて子どもとしっかり向き合い、日常の作業の中に手先を使う動きを取り入れるよう提案する。クーポンを切り取る、一緒に料理をする、学校に行く途中で石を探す、コップに水を注ぐ、お風呂でスポンジを絞る。粘土やクレヨンは手先を使うし、長持ちもする。
こうした作業は、画面にはかなわないことを理解しておこう。「テレビを消して『さあ、読書の時間だよ』と言っても強く反発されるでしょう」とホーンベック氏は指摘する。そうしたバトルを避けるには、まずは作業を先にやって、画面をオンにしないことだ。
バーネット氏も同じ考えだ。「画面から離れさせましょう。子どもたちは本を『スワイプ』しようとしています。警戒すべき兆候です」
あわせて読みたい
-

- ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国
- ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国 毎年4月30日の夜、1万人近くが英国スコット…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- NHK福岡で大河ドラマ「べらぼう」巡回展 衣装やサイン色紙など展示
- 展示会「大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』NHK全国巡回展in福岡局」が5月3日から、NHK福岡放送局…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[芸術]
-

- 66歳・月の年金20万6400円「孫に会える。以前より楽しみが増えた」おひとりさま男性の老後生活
- 老後の心配事といえば、やはりお金。現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか…
- (All About)[省エネ]
-

- 子どものハブラシの色は何色? 無意識に選んでいる親の思い込み
- いいんじゃない? / (C)島村華子、てらいまき/KADOKAWA日々の暮らしの中で困っていた子どもの行動が、…
- (レタスクラブニュース)[新商品]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社