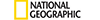子どもを夢中な「フロー状態」に導くには、創造性を育み幸せに

7歳のエミーさんはドラゴンに夢中だ。
新型コロナウイルスのパンデミックの間、エミーさんは「つまんない」を連発していた。「それがドラゴンと出会ってからは、生き返ったみたいでした」と、米国イリノイ州に住む二児の母、リジー・グッドマンさんは言う。エミーさんは何時間も自分の部屋にこもってはドラゴンの百科事典作りに励むようになり、ドラゴンにまつわる情報をあれこれ書いたり、ドラゴンの絵をこと細かに描いたりしていた。
「着替えておいでと部屋に行かせたら最後、ドラゴンの世界に入り込んでしまって、『戻ってきなさい』って言って連れ戻すはめになるんです」とグッドマンさんは笑う。
ドラゴンに出会う前は、エミーさんは専門家が言う「虚脱感」に陥った状態だったとみられる。
「落ち込んでいる状態ではないのですが、最適な形で機能していない状態です」と、米ホフストラ大学の心理学教授である ジェフリー・フロウ氏は言う。
心理学者によると、人が満ち足りた幸せを得るのは、何かに夢中になっているときや、誰かと重要な関係性を築いているとき、達成感とともに技能や知識を得られるような目標に向かっているときだという。
不確かな状態や恐れなどは、子どもの活気を奪う要因になる。「現代の私たちは、脅威や安全に対する感覚が過度に高まりすぎて、何かにチャレンジすることが難しくなっています」とフロウ氏は指摘する。
しかし、エミーさんがドラゴンに出会ったように、虚脱感に対抗する手段はある。「フロー」だ。フローとは、何かに没頭している状態を指し、充実した幸せをもたらす特徴的な要素をいくつも備えている。
フロー状態の子どもは、自分がしていることに完全に夢中になっていて、時間がたつのを忘れ、食べる・寝るといった身体的な欲求すら忘れてしまう。
「人はみな生まれつき、成長したいという欲求を持っています」とフロウ氏は言う。「子どもがフロー状態になるよう働きかけることは、子どもが自分のポテンシャルを模索し、発揮するのに役立ちます」
次ページ:フロー状態のとき、脳では何が起きているのか
フロー状態の脳では何が起きているのか
人がフロー状態のとき、脳では実にさまざまなことが起きていて、その全体像は単純ではないことがわかっている。
米カリフォルニア大学サンフランシスコ校の外科医であり神経科学者でもあるチャールズ・リム氏は、2008年2月27日付けで学術誌「PLOS ONE」に発表した研究で、ジャズミュージシャンがピアノを演奏しているときの神経活動を調べた。
すると、「即興で演奏しているとき、前頭前皮質(自己を客観的に観察することに関わる領域)の広い範囲が止まったようになっている」ことがわかった。
また、「クリエイティブな活動をしている間は、感覚処理や運動処理を司る部分(の活動量)が増えているとみられる」とリム氏は語る。同様のパターンは、フリースタイル・ラップのミュージシャンや、コメディアン、風刺漫画作家にも見られた。
簡単に言うと、人が没頭してフロー状態にあるとき、自意識は消えるが、している活動に対する意識が高まることが、脳をスキャンしたところわかった、ということだ。フロー状態に入ったダンサーは、例えば、おそらく筋肉の痛みは感じていないが、自分の動きを左右する曲には超敏感に反応している。
このことは、子どもにとってどんな意味を持つのか。何をするかによって、またその人の専門の度合いによって(例えば「絵を描くのが好きな子ども」と「プロのアーティスト」の違い)、フローの状態には複数のレベルが存在するのではないか、とリム氏は推測する。
現在進められている研究の中で、リム氏のチームは、音楽的な訓練を受けていない9〜11歳の子どもを対象に、即興演奏中の脳の活動を調べた。ミュージシャンを対象にした実験と同様に、暗記した曲を演奏しているときと、即興で演奏しているときの脳のパターンを比べた。実験は、どんな音を鳴らしたとしても絶対に間違っているようには聞こえないような仕組みで行われた。
「プロのミュージシャンと比べると、子どもの脳の活動はかなり控えめでした」とリム氏は言う。「子どもの脳のパターンと、訓練を経た大人の脳のパターンには、どのような関連性があるのかという興味深い疑問が生じました」
とはいえ、「子どもが暗記から即興に移ったとき、つまり丸暗記から完全に夢中になれる活動に移ったときの脳には大きな違いがある」ことは明らかになった。今後続く研究によってさらに詳細が判明することだろう。
次ページ:子どもをフロー状態に導くには?
神経化学の観点から言うと、フロー状態では、学習や記憶、感情の制御に関わる神経伝達物質のドーパミンが重要な役割を担っている。
「実際、フロー状態は、脳のドーパミン作動性回路(ドーパミンが脳内を伝わる経路)をうまく利用している」と、英ロンドン大学の心理学教授ジョイディープ・バッタチャリア氏は言う。氏は、フロー状態になる頻度が高い人のドーパミン作動性回路は「時間をかけて徐々に再編成され、形作られる」のではないかと推測する。
したがって、定期的にフロー状態になることで、学習意欲や感情をコントロールするスキルを向上させられるのかもしれない。
2013年11月22日付けで学術誌「Frontiers in Psychology」に発表された研究で氏は、ピアノを学ぶ学生のフロー状態に入る能力と、感情知能(感情を理解、管理、活用する能力)の間には関連があることを示した(ただし、研究は相関関係を示すものであって、因果関係を示すものではない、と氏は注意を促している)。
子どもがフロー状態になるよう働きかけるには
落書きや積み木で高層ビルを作り上げることに夢中になる子どもをみたことがある人ならわかるだろうが、「子どもはフロー状態になる傾向を生まれつき、本質として持っています」と、バッタチャリア氏は言う。
だが、ちょっとした後押しが必要なときもある。子どもがフローの恩恵を受けられるよう、いくつかアドバイスを専門家からもらった。
1. 子どもが何に興味をもつかを探る
フロー状態になるには、本人の内側から生じる動機が非常に重要であるため、子どもが何に夢中になるかを探ることが大事だ。
「何に興味があるのか、子どもと話をしてください」と、ミシェル・ハリス氏は言う。氏は米国ニューヨークに拠点を置く認定臨床ソーシャルワーカーで、親たちのためのコーチングやワークショップなどのサービスを提供する会社「ペアレンティング・パスファインダー」の創設者だ。
また、子どもにただ「これをしなさい」と言うのではなく、子どもに自分で考えさせるべきだ、とも説く。自主性が認められると、続ける可能性が高くなる。年少の子どもの場合は、「自分で思いつくのが大変そうであれば、親がアイデアを出して提案してもかまいません」とアドバイスする。
どんな活動が「フロー状態」になるかは、個人によって大きく異なる。「何が子どもの心に火を付けるのか、お子さんのために探ってください」と、米ラトガース大学の教育心理学者デビッド・シャーノフ氏は言う。
「こうした類いのフロー状態になる活動を積み重ねていけばいくほど、子どもはやる気や意義を感じるようになります」
次ページ:後押しのポイント、あと3つ
2. 気が散るものを排除し、邪魔されない時間を確保する
私たちが生きている時代は気が散ることばかりで、予定もぎっしり詰まっている。どちらもフロー状態を壊しかねない。「テレビを消して、気が散りにくい場所を見つけてください。そして、今はただ、自分が取り組んでいることを楽しむ時間だよ、と子どもに伝えてください」とハリス氏は言う。
フロウ氏も同意見だ。「何も決めず自由に遊ぶこと、しかもたくさん遊ぶこと。それが不可欠です」。例えば、フロウ氏の11歳の娘と14歳の息子は、興味のあることをする自由な時間を十分に確保するため、課外活動は2つまでにしているという。
3. 子どもに「足場」を用意してサポートする
フローには微妙なバランスが求められる。興味を持ち続けられる難易度は必要だが、がっかりしてしまうほど難しすぎてもいけない。子どもがヘルプを必要としがちな最初の頃は親が「足場」となるようなサポートを用意して、このバランスを保つ必要がある。子どもに自信がついてきたら、親は手を引く。
レゴを例に挙げよう。まずは「説明書の通りに作れば、何ができあがるのかがわかるキットから始めるのがよいでしょう」とシャーノフ氏。子どもが基本を身に付けたら、何か新しいものを一緒に作るとよい。
「煙突の色は何色にする?」「ここのドアは外開き、それとも内開き?」など、子どもに尋ねるのを忘れないように。ただし、主導権は子どもに握らせる。
フロー状態をもたらす活動に親が一緒に取り組むことは、子どもとのつながりを生む非常によい方法でもある。
家族でも友達でもメンターでも、他の人とつながっていると感じられると、フローを促し、虚脱感にも対抗できるかもしれない。例えば、学校におけるフローに関するシャーノフ氏の研究では、教師と同級生からのサポートは、生徒の積極的な参加につながることがわかった。
「フロー体験を友だちと共有することは有意義で、絆を生むきっかけになります」とシャーホフ氏は言う。さらに、友だちやメンターから即座にフィードバックが得られれば、子どもは目標(あるいはそれ以上)を達成しやすくなる。
4. 成果を重視しない
親が成果や結果を重視すると、やっていることを楽しむ気持ちを失わせてしまうかもしれない。「ピアノを弾くのにモーツァルトになる必要はないし、バスケットボールをするのにマイケル・ジョーダンになる必要もありません」とリム氏は言う。
そうではなくて、子どもがもう少し自由に、手順やルールなどに縛られずに取り組めるようにしよう。出版のことは一切考えずコミックブック制作に取り組むのもいいし、お気に入りの映画のサウンドトラックに合わせて歌うのもいい。
結局のところ「創造性は万人に備わっている」というのがリム氏の考えだが、さらに磨きをかけるには訓練が必要だ。
「子どもがこうした活動に取り組むとき、脳内では創造性が育まれています」とリム氏は語る。そして子どもがフローを通じて自身のクリエイティブな本質に触れるようになればなるほど、大人になったとき、そうしたスキルを生産性へと発展させられる可能性が高くなるだろう。
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社