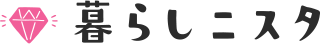日本の失踪者は無数にいて、警察が積極的に探してくれることはない|うさぎの耳〈第六話〉谷村志穂
◀前の話 「ケチだと思われるの、みっともないでしょ」一人一万八千円の寄付金を、義母が財布から渡してくれる。||うさぎの耳〈第五話〉谷村志穂
急に、まるで改めて祝福されるように相手の声が耳元に広がった。
「お引っ越しされたのですね。新しい住所変更、このお電話でもたまわれますが」
馬術部の同窓生たちが、馬場で結婚パーティを開いてくれた。テーブルに野の花を飾り、私にはブーケも。皆でシャンパーニュのボトルを開けた。そうだ、その時のブーケにもにんじんが刺さっていたのだった。二人で可愛がっていた馬はもう高齢だったが、にんじんを美味しそうによく食(は)んだ。馬独特の、口を捻るような食べ方で。

「高山さん、もしもし?」
「すみません」
「あの、では百周年の同窓会の連絡も行ってないですか?」
「ええ、たぶん」
もしかしたら夫はどこかで受け取っているのかもしれないが。
「よかったら、いかがですか?」
都内のホテルの会場と、日時が知らされた。
「お忙しいですか?」
忙しいなんてことが、あるはずがない。
「検討します」
「あ、ですが、しめきりは明日です」
「…参加します」
「お二人で?」
「いえ、一人で」
慌てて、理玖のバスケットに入れてあったノートとクレヨンを出し、メモを取った。
理玖は、莉子が預かってくれることになった。
ケチな家だと思われたくない義母は、同窓会の参加費を出してくれた。
一枚だけ、残してあった紺色の薄地のワンピースを着て、髪は一つに結び、耳元にピアスをつけた。
莉子のアパートまで理玖を連れて行くと、彼女が髪の毛の毛先を少し巻いてくれて、気持ちよく送り出してくれた。
仲間たちに会いたいというよりは、私にはこの同窓会に密かな目的があった。
もう何度も警察署の前を行き来して、届け出を出すべきかどうかを迷ってきた。けれど、日本の失踪者は無数にいて、犯罪にでも巻き込まれていない限り、警察が積極的に探してくれることはないのは想像がついた。高山隆也が、神奈川県の失踪者リストに載るだけのはずだった。
盛大な式典、OBの代表としてずいぶん上の代の先輩が登壇し、開会の挨拶をする。代わって、乾杯の挨拶。
同期ごとの丸テーブルに座る。
「美夏、元気してた?高山くんは?」
「二人が連絡つかないって、幹事が困ってたよ」
テーブルの上で一気に泡立つように会話が弾けていき、私はしばらくその輪っかがあちらこちらで生まれ、そこから編み目が立ち上がっていくような様子を見つめていた。
幾つもパペットになって、一つまた一つと、席に座っていく。まるでそんな風にも見えた。
それぞれ自己紹介や近況が話された。
「六十期は、結束が固かったよね」
コンサル関係の仕事についたという、美咲の耳元で、大きな南洋パールピアスが揺れている。
「だけど、高山たちの結婚っていうのが衝撃だったからさ。本当は、二人が中心になって、盛り上げてくんないと」
自動車メーカーに勤めているという山喜田はだいぶ恰幅がよくなった。
「それはまあ、部長の役ってことでいいんじゃないの?」
商社勤務の、野本は細身で見かけがまるで変わっていない。
「いや、俺はまだマネージメント部課長」
ダジャレのような会話が続いた。
私の番になった。
「高山は、今日は仕事?」
野本が、訊ねてきた。
「わからない」
手に汗が滲んできた。
「わからないって?」
皆の視線が、訝しげに、そしてどこか興味本位に集まっていた。
「ごめんね、こんな場なんだけど、お願いに来た。久しぶりに来て、図々しいけど、みんな助けて欲しい。子どもが生まれて少しして、隆也はいなくなったの。仕事場からも、どこからも消えちゃった」
隣の野本は、自分でビールを継ぎ足していた。
「美夏って、こんな言い方はよくないかもしれないけど、確か身寄りがなかったよね」
美咲がフォークで皿の上に落書きをするように動かしながら言う。
「お子さんは、元気なんだよね?高山からは少し聞いてたから」
先に母親になった由希奈の遠慮がちな口調が、逆に心に刺さった。
「そう。障がいをもって生まれたけど、もうたくましいよ」
「何やってるんだよ、あいつ」
山喜田が、首を横に振る。
「待ってるつもりだった。何も考えないようにして。だって考えても、さっぱり何もわからなかったから。でもね、もう探そうと思ったの。どうしてなのか知りたいもん。あの子だって、今に感じてしまう。私が迷ったままだって」
「探さないと、始まらないでしょ」
と、野本は言って、続けた。
「まず、もう一回乾杯しよ。美夏、よく来たよ」
惨めだとかそんなことは、何も感じなかった。ただ、必死だった。皆の手にあるグラスの中の泡立ちが、束の間こんなことは夢なのだと思わせてくれた。
(つづく)
◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。
あわせて読みたい
-

- 不安なときこそ美味しいものを食べて、心をほぐしたい災害時に。【ボローニャ】の缶入りデニッシュがAmazonで売り出し中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[健康食材]
-

- 首からじんわり、氷の涼しさ。猛暑も快適に過ごせる【ミズノ】のネッククーラーがAmazonに登場中‼
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[アウトドアグッズ]
-

- 六本木に「みんなのカレー」 スパイス30種をかけ合わせ
- カレー専門店「みんなのカレー」(港区六本木4、TEL 03-6910-5500)が4月18日、六本木にオープンした。(…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[お酒,野菜,ビール]
-

- 世界初。遮光・断熱・発電・給電を同時に実現するロールスクリーン型太陽光発電で、
- 世界初。遮光・断熱・発電・給電を同時に実現するロールスクリーン型太陽光発電で、Image: LIXIL 一般家庭…
- (Gizmodo Japan)[寄付]
-

- ひと目でわかる今日の傘マップ 5月9日(金)
- ひと目でわかる今日の傘マップ 5月9日(金)2025/05/09 06:12 ウェザーニュース今日5月9日(金)の外出の際に…
- (ウェザーニューズ)[北海道]
-

- 崎陽軒「感謝の気持ち」詰め合わせた「母の日弁当」と「父の日弁当」
- 崎陽軒(横浜市西区高島2)は5月8日から10日まで「母の日弁当」、6月13日から6月15日まで「父の日弁当」を…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[神奈川県]
-
- 「嘘だろ…このタイミング!?」絶対に避けられない“赤ちゃんトラップ”の正体!これが想定外だらけの0歳育児の現実だ!!
- 授乳もおむつ替えもしたのに、なぜか赤ちゃんが泣きやまない…!かと思えば、うんちやおしっこをし…
- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.