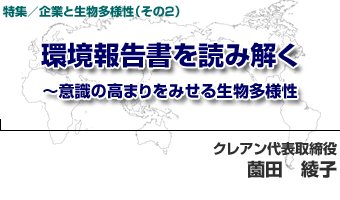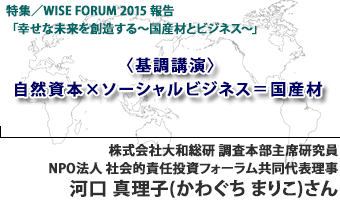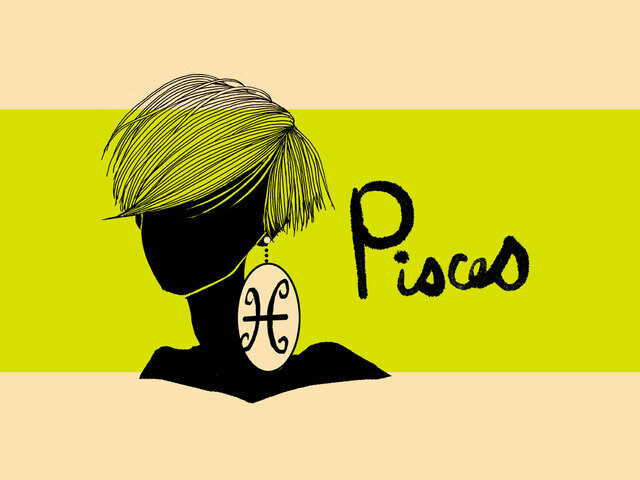このコンテンツは、地球・人間環境フォーラム発行の「グローバルネット」と提携して情報をお送りしています。
第65回 環境報告書を読み解く〜意識の高まりをみせる生物多様性
- 2009年6月11日
このコンテンツは、「グローバルネット」から転載して情報をお送りしています。
無断転載禁じます
生物多様性の項目記載の傾向
企業が毎年発行するCSR(Cor
-porate Social Responsibility:企業の社会的責任)レポートでは、CSR方針や体制、環境や社会的側面におけるマネジメントやパフォーマンスについて、目標から成果、さらにネガティブ情報およびその改善状況などを知ることができる。
今年のレポートで「生物多様性」について記載されている傾向を見てみよう。企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)が行った生物多様性に関する563社の環境報告書調査結果によると、2007年度報告書において「生物多様性」という言葉を用いている企業は3割程度であり、2008年度報告書では、「生態系」という言葉を含むと5割まで増加している。生物多様性の取り組みを本業と社会貢献で分けてみた場合では、2007年度までは社会貢献が主であったが、2008年度には本業における取り組みも増加傾向となっている。
社員の意識と行動を方向づけるCSR方針
ここで重要なのは、企業内での社員の意識と、その意識が取り組みに反映されているかどうかである。なぜなら、マネジメントやパフォーマンスの中に生物多様性への配慮が含まれていても、意識的に取り組まれない限り、トピック的あるいは単発的になってしまうからである。
企業の意識が最もよく反映されているのはトップコミットメントである。経営トップが「地球環境(生物多様性を含む)」をどう捉えているのか、地球環境にもたらすマイナス要素を認識した上で、どう解決しようとしているのかが述べられていれば、意識は高いといえる。さらに「持続可能な社会(あるいは地球の未来)に対する考え方や取り組み方針」についても言及されていれば、その姿勢は高く評価できる。
CSR方針の中で生物多様性の視点が明確に含まれていれば、企業が持続可能な未来の地球、持続可能な社会に向けて、どう考え、どう取り組もうとしているかがわかる。もしも、CSR方針に自社の持続可能性しかなければ、地球環境や生物多様性とはかけ離れていることになる。
CSR方針が環境マネジメントへ
生物多様性への具体的な取り組みが環境マネジメントに落とし込まれているかが、次のポイントである。さらに調達から開発、操業、廃棄までのライフサイクル、従業員の人材育成のための教育、そして地域社会、これらすべてがパフォーマンス結果として表れていることである。従来は、環境マネジメントの範囲を、法令等の規定に基づいた環境基準をクリアしていれば十分と考える企業がほとんどであった。
例えば、ある地域に立地する工場を考えてみると、生物多様性に配慮したマネジメントとは、排水先の河川生態系や大気排出の周囲の森林生態系、地域の生態系サービスを享受する住民の生活・文化など、外の自然環境や住民に配慮することであり、単純な環境負荷低減とはその点が大きく異なる。
従来のグリーン調達も環境基準や合法性に基づけば十分と考えられていた。ところが、生物多様性に配慮した調達では、サプライチェーンマネジメントの必要性も含め、調達先の生物多様性に配慮しているかどうかも問われてくる。
生物多様性におけるベストコミュニケーション
生物多様性保全に取り組む国内企業のコミュニケーションに注目してみたい。企業が生物多様性に取り組むためには、そこにはステークホルダー・エンゲージメントが必要不可欠といえる。
●鹿島建設
「鹿島生態系保全指針」を2005年8月に制定し、取り組みを進めているが、本来、従業員自らが率先して生物多様性保全のための研究を始めた経緯がある。全社環境委員会生物多様性部会が作成した社内教育資料「鹿島の生物多様性・生態系保全入門」は、社員の意識啓発を図るのに役立っている。これらの資料やイントラネットを通じて、本業における生物多様性保全の配慮事例や配慮しなかった場合のリスク情報も社内共有している。
●富士ゼロックス
CSRの理念として「持続可能な社会」、さらに「持続可能な地球(生態系)」を目指すと明言。とくに、商品生産に必要な部品を購入する取引先に対するCSR調達を本格的に展開し、環境・人権労働・企業倫理分野を網羅するCSRセルフチェックリストの作成、取引先への説明会の開催、回答回収、結果分析、フィードバックシートの返送、訪問診断員教育などを実施している。すでに本業において生物多様性保全に向けての配慮が具体的に進んでいる企業の一つである。
●住友林業
トップコミットメントで「サステナブルな社会に向けて」として、四つの重要課題の策定を報告している。重要課題の一つ、「持続可能な森林から木材製品や資材を供給する」では森林認証材および国産材の利用促進への取り組みが紹介されている。インドネシア国内での植林事業では「社会林業」の考え方のもと、林業公社、農園公社、地域住民と協働する。地域住民に苗木を無料で配布し、森林管理の方法を指導した上で5〜7年間育ててもらい、収穫期を迎えた木を買い取ることで、住民の生活向上に貢献しているのは、生態系と社会性を併せ持つ生物多様性保全そのものであるといえる。
●アレフ
本業の飲食産業において、食とエネルギーの地産地消、自給自足と循環型コミュニティの形成を目指している。地域の団体と連携しながら生態系に配慮して休耕地を活用したナタネプロジェクトや、農薬や化学肥料を使わず米を収穫する冬期湛水水田として生物モニタリングをしながら生物多様性保全を目指した「ふゆみずたんぼプロジェクト」。本業における生態系の保全と次世代教育を兼ねたこれらの取り組みは生物多様性への社会貢献でもあり、生態系にプラスになるものだ。
人間活動が自然に働きかける場合、社会貢献といえども生物多様性にプラスになるかマイナスになるかには不確実な面が多分にある。そのために多様なステークホルダーの参画による生物および社会のモニタリング評価が国内および途上国でも必要とされる。 社会のモニタリングの目的は、豊かな生態系によって営まれる地域社会の暮らしの保全状態を図ることといえる。言い換えれば、自然と人との「いのちのつながり」を意識して行動することそのものが生物多様性保全ともいえる。 生物多様性保全への取り組みとは、単に植林をすることや里山づくりをすることでもなく、開発した分だけ保全するというようなオフセットでもない。これからの取り組みは科学的かつ社会的な質が問われてくるだろう。でも、いつの時代も忘れてはいけないのが、いのちのつながりを意識した自然への畏敬の念と感謝の気持ちなのかもしれない。
海外企業の先進事例 パタゴニア
米国カリフォルニア州に本拠を置くアパレル産業パタゴニアでは、陸海域を問わず豊かな自然環境や貴重な生態系を開発や有害化学物質から保護する活動を支援しているのが特徴的。素材調達時の環境配慮は当然の義務で、野生生物保護区の保護活動のほか、環境的に大きな問題を抱えるダム建設や核燃料再処理工場における反対キャンペーンヘの取り組みも行う。注目すべきは、1985年より環境問題解決の支援として税引き前利益の10%を草の根運動の環境活動グループに寄付することを定め、その後、売上の1%もしくは税引き前利益の10%、いずれか多い金額を寄付することを誓約化した点。パタゴエアでは、日本支社を含め、他の企業の助成金リストから漏れたり、拒否 されたりした革新的な草の根運動グループを選定しているのもユニークだ。生物の生息地、自然環境の保護のために、戦略的に果敢に戦う熱き活動家たちを支援している。
(グローバルネット:2008年12月号より)