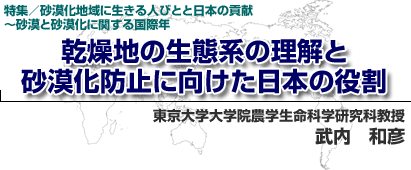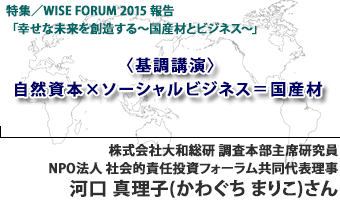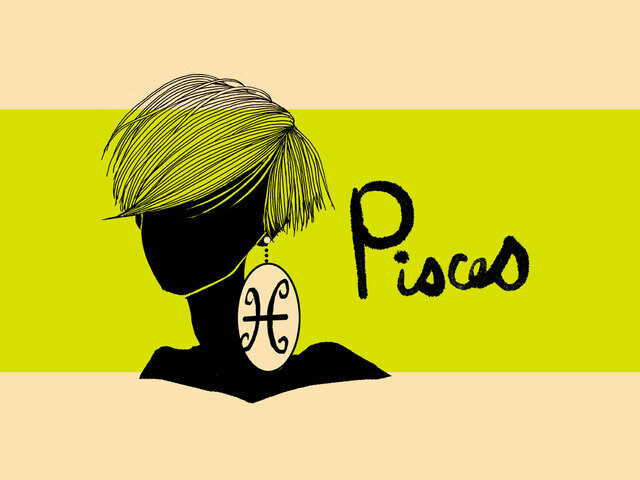|
乾燥地は、文字通り「乾いた土地」であり、降水量が少なくても生育可能なステップやサバナと呼ばれる草原や疎林の植生景観が見られる。イネ科の草原やアカシアの疎林に代表される乾燥地の植生は、干ばつを含む長い乾季を耐え、わずかな降水量や地下水に頼って生長する特性をもっている。自然が手厚く保護されたアフリカの国立公園では、ライオン、ヒョウ、サイなど大型野生動物が、草原や疎林を悠々と闊歩する姿を見ることができる。
しかし、そうした自然が残るのは世界の乾燥地のごく一部にすぎず、ほとんどの乾燥地は人間が放牧や農耕に使っていて、景観も大きく変貌している。サハラの南縁に帯状に広がるサヘルは、世界で最も砂漠化の進んだ地域の一つである。砂漠化の原因は、増加する人口を賄うための家畜の過放牧や農産物の過耕作などの人間活動である。遊牧民を定住化させる政策がとられている場合、環境への圧力は定住地に集中するため、砂漠化はますます増幅される。
こうした砂漠化が深刻な問題として国際的に認知されたのは、1977年にナイロビで開催された国連砂漠化会議である。この会議は、それに先立つ68〜73年のサヘルの大干ばつが大きな契機となって開催された。こうした干ばつがあっても、伝統的な遊牧であればより降水量の恵まれた地域に移動することで、被害を最小限に回避することができる。しかし、遊牧民の定住化や農耕地の開発が進んだ後では、被害の発生を食い止めることは難しい。
国連砂漠化会議の議論をふまえて、ナイロビに本部をもつ国連環境計画に砂漠化対処プログラムが設けられたが、十分な成果を挙げることはできなかった。その原因の一つは、砂漠化が深刻化しているのは主に途上国の乾燥地であり、人口問題や貧困問題という解決困難な問題と深く関係していることにある。92年の地球サミットでアフリカ諸国から砂漠化対処条約の必要性が提起されたのは、地球温暖化などの議論が進む一方で、途上国の環境問題が忘れ去られることに対する危機意識があったからである。

96年に発効した砂漠化対処条約は、今年で10年を迎える。これを記念して設けられたのが「砂漠と砂漠化に関する国際年」である。世界各地で、この国際年を記念した催しが行われている。日本は98年から締約国となり、それ以来、締約国会議などに参加している。私も、ブラジルのレシフェで開催された第3回締約国会議より毎回、科学技術委員会に出席し、科学技術の立場から日本を代表して意見を表明している。
私は、第3回締約国会議の決議を経て科学技術委員会に設置された早期警戒体制アドホックパネルのメンバーに選出され、ボンで開催された第1回パネル会合では、さらに議長に選ばれた。日本政府の支援もあって、第2回パネル会合は、山梨県富士吉田市で開催した。早期警戒体制とは、行政組織や地域住民に的確な情報を伝え、被害軽減のための回避行動を促すものである。このパネル会合では、早期警戒体制を、砂漠化防止のための長期的早期警戒体制と干ばつ防止のための短期的早期警戒体制に区分し、前者については世界的に方法論が未確立であることから、パイロットスタディを開始すべきだと勧告した。
また、環境省地球環境総合研究推進費の採択を受けて「北東アジアにおける砂漠化アセスメントおよび早期警戒体制構築のためのパイロットスタディ」を中国やモンゴルの研究者の協力を得ながら実施している。風食や水食に対する潜在的な影響を広域的・長期的にモニタリングするとともに、いくつかのモデル地域において、土地条件ごとの放牧圧に対する植生の劣化と禁牧による植生の回復を評価し、それぞれの土地条件に応じた土地利用指針を提示しようとしている。砂漠化早期警戒体制のための方法論が確立できれば、他の乾燥地にも適用可能と考えている。

ここで重要なことは、乾燥地の植生の劣化と回復は、必ずしも可逆的ではないということである。干ばつで劣化した植生は、降水量の増加に伴って、もとの植生に回復する。しかし、人間の圧力が加わって植生の劣化が激しくなり過ぎると、その圧力が取り除かれても、もとの植生には回復できない。それは、植生を支える土壌有機物などが除去されることによって、かろうじて維持されていた植物と土壌有機物の関係が一挙に破壊され、生態系の不健全化が引き起こされてしまうからである。
それゆえ、そのような深刻な事態に陥る前に、対策を講じることが有効な手段となる。植生の劣化が不可逆的な砂漠化をもたらす閾値をフィールド調査によって確認し、その成果を、リモートセンシング等を使って広域的に広げていこうとしている。もちろん、そうした対策は地域住民の理解と協力なしにはなし得ることはできない。そこで、こうした科学的な知見を行政組織や地域住民にいかに伝えるかが重要になる。

私たちは、早期警戒体制を地域住民が使えるようにするために、植物指標を活用できないかと考えている。植生が劣化すると、そこに生育する植物が変わる。裸地になってしまう前に、不可逆的な変化が起こる閾値を示す植物を見いだすことができれば、フィールド調査の結果を、指標植物を使って表現することができる。牧畜民にとっては植物こそが生活の基盤であり、長年慣れ親しんできた環境でもある。彼らの伝統的知識と科学技術の成果による早期警戒体制を組み合わせることで、大きな効果が出るものと期待している。
このような考え方は、砂漠化対処条約科学技術委員会に設置された伝統的知識に関するアドホックパネルでも議論された。また、イタリアのマテラには伝統的・地域的知識に関する研究センターが設立された。伝統的知識の活用は、地域住民のもつ潜在的な能力を引きだし、自らの主体的な努力によって砂漠化防止の取り組みを促すというキャパシティ・ディベロップメントの考え方とも付合する。もちろん、伝統的知識が発達した当時の状況とは人口や環境が大きく異なっているので、伝統的知識のみを解決手段とすることは現実的ではないが、これまでの歴史的・文化的な営みの延長線上に持続的な社会を展望する上でも伝統的知識の再評価は重要である。

日本の砂漠化防止に対する貢献についても、日本の先端技術を移転して途上国の砂漠化防止に貢献するというこれまでの考え方を改めるべきであることは明らかである。実際、日本の環境ODAは、より地域社会と親和する参加型の取り組みに対する支援が主流となり、かつての日本の技術を丸ごと途上国に移転しようとしていた頃とは、まさに隔世の感がある。一方で、乾燥地域の生態系の現状をよく理解していないための問題も残されている。
最近、黄砂の発生を防止するための事業として、モンゴル・ゴビ地域の植林事業が挙げられることが多い。しかし、この地域は、もともと樹林が成立しえない気候帯にあり、河川沿いなどを除けば、樹林を成立させるためには地下水を汲み上げて緑化をするしかない。こうした緑化は、すでに一部実施されているが、いずれは地下水の枯渇を招くであろう。このような過ちを未然に防止するために、砂漠化防止のための環境ODAでは、まず対象となる乾燥地の生態的特性をよく把握し、地域住民の伝統的知識によく学び、その上で、日本が貢献できることを虚心坦懐に考えていくべきであろう。
|