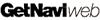指輪型ならではの「控えめさ」がイイ。issinのスマートリング「Smart Recovery Ring」を選ぶ理由
ウェアラブルデバイスの代表格であるスマートウォッチは、決済、健康管理、通知確認などいくつかの機能を持ちあわせた製品が一般的です。一方、近年少しずつ広がりつつあるスマートリングは、そのコンパクトさと引き換えに機能を絞った製品が大半。今回試したissinの「Smart Recovery Ring」も健康管理目的、特に日々の回復度合いを改善することに特化しています。
それならいろいろなことができるスマートウォッチでいいんじゃない? と思う人もいるでしょうが、実際に使ってみたことで、スマートリングならではのメリットが見えてきました。
ウェアラブルデバイスでもトップクラスの軽さとコンパクトさ

睡眠は疲労回復やストレス解消だけでなく、肥満や高血圧など生活習慣病の予防にもつながるのは広く知られた話です。難しいのは、単純に長く寝れば良いというものではなく、心身をしっかりと回復できる良質な睡眠を取る必要があるということ。
Smart Recovery Ringは、その名のとおり身体のリカバリーに特化したもので、心拍数、活動量、血中酸素濃度、皮膚温などを24時間モニタリングし、「どのくらい回復できたか」を可視化できるのが最大の特徴です。
実物を手にして最初に感じたのは、本体の軽さとコンパクトさ。重さは約3g、薄さは約2.2mmと小型軽量。また、表面素材はチタン製の落ち着いた質感で、ビジネスシーンでつけても違和感がなさそうなのは重要なポイントだと感じました。

防水規格はIP68/5ATMに準拠。IP68は防水防塵精度の等級で最高レベルの保護性能を意味します。また、5ATMは5気圧防水を意味するもので、水深50mで10分間の防水性能を保つことが可能。つけたままで手を洗うなど、普段の生活で起こる水濡れはまったく問題ありません。
また、電池持ちはかなり長く、カタログスペック上では最大7日間の連続使用が可能となっています。
常時着用デバイスに必要な「つけていることを忘れる」感覚

心拍数などを常時モニタリングするデバイスの場合、つけていることを忘れるくらいでないと煩わしくなり、長期間使い続けることが難しくなってしまいます。その点、この製品は軽さ・薄さに加え、落ち着いた質感、防水性能、電池持ちなど、あらゆる面で「つけっぱなし」を強く意識した設計になっていると感じました。
一方、スマートウォッチの場合は異なります。例えばApple Watch Series 10の場合、重さは約30〜40g程度とかなり軽量ですが、スマートリングには敵いません。また、バッテリー駆動時間はカタログ値で18〜36時間なので、1日おきくらいの頻度で充電が必要です。
健康状態、特に睡眠を常時モニタリングするという役割に限って言えば、スマートリングの方に分があるといえるでしょう。
なお、「つけていることを忘れる」ために、適切なサイズを選ぶことは非常に重要です。購入前にはサイジングキットが利用できるので、念入りに試してから購入することをおすすめします。

データ確認、運動、食事管理などを行う専用アプリ

スマートウォッチと違って本体にモニターがついていないので、計測結果の確認などは専用アプリ「ウェリー」を使って行ないます。メイン画面に一番大きく表示されるのは、リカバリー率(上画像の囲み①参照)。その下には前日の睡眠時間と、当日の活動量やストレス量などが表示されています。②部分のアイコンは左から「一週間の睡眠時間」「当日のストレス」「当日の活動量(歩数)」に対応していて、それぞれの推移をグラフで見比べることが可能です。

また、③の「データ詳細」を選択すれば、各種数値をより詳しく知ることが可能。例えば、睡眠のデータを見てみると、何時にどのくらいの深さで眠っていたかなどを細かく知ることができます。

こうした各種データを見比べると、どんな行動をすればリカバリー率が変わるかが次第にわかるようになるのは新しい発見でした。筆者の場合、以下のような状況でリカバリー率が大きく下がるようです。
- 深酒をした日
- 休日に昼寝を多くしたとき
- リカバリー率を上げようと、運動や散歩を多くした日
1と2はリカバリー率が下がることがある程度予想できましたが、3は少し意外な結果でした。過度な運動は逆効果のようです。行動量、心拍数の推移、睡眠の深さなどを見比べることで、一日の行動に対しての意識が高まるのは、常時監視型デバイスの大きな魅力だと感じました。
そして、もうひとつ注目したいのが、④部分です。ここには常時メッセージが表示されており、タップすることで現在の心身の状態に合わせた運動やリラックス方法が提案されます。
この提案が非常に絶妙で良い感じ。比較的リカバリー率が高く、各種数値も落ち着いている場合は「深呼吸」や「リラックス」などを促されることが多く、リカバリー率が低い場合や一日の運動量が少なすぎる場合は、「10分間の散歩」や「5分間の運動」などが提案されることが多いように感じました。

運動を選択した場合、そのときの自分に合ったメニューが都度作成され、動画を見ながらエクササイズをすることができます。スクワットや飛ばないバーピーなど、その場でできるメニューで構成されているので、自宅で気軽にできるのは良いと思いましたが、職場やカフェなどでは難しいメニューが多かったのが少々残念なところ。周りの目があるところでもできる簡単な運動を選べる設定などがあれば、より良いと感じました。

そして、メイン画面左下の⑤のアイコンをタップすると対話型のAI「ウェリー」を起動できます。ここでは、食事の写真を取って送ると、カロリーやPFCバランスを表示してくれて、ちょっとしたアドバイスを受けることが可能です。

この対話AIを利用すると、ダイエットを目的とした詳しい食事アドバイスや、運動のオリジナルプラン作成などもできるようですが、それは別売りの「Smart Bath Mat」のユーザー限定とのこと。睡眠管理以外にダイエットも目的とするなら、こちらも合わせて購入するのがおすすめです。

「控えめ」であることのメリットとデメリット
Smart Recovery Ringを一週間ほど試用して感じたのは、本体・アプリともに「控えめ」であることを念頭において設計されたサービスだなということ。
本体は軽量・コンパクトで落ち着いた質感。充電の手間も少ないので、つけていることを忘れるほど控えめです。そして、アプリの機能もかなり控えめだと感じました。試す前は、頻繁に通知が来て運動や休憩を促されるものかと思っていましたが、実際一週間の試用期間のうち、通知が来たのは一回のみ。それも、入浴時に外してそのままつけ忘れたときに「リング着用を忘れていませんか」という通知があっただけです。
このように、あまり主張しすぎない製品であることが、当初はデメリットに感じることもありました。外出時にリングをつけていることも、アプリの存在も忘れてしまい、帰宅時にようやく思い出してアプリを立ち上げるということがあったときには、「もう少しサジェストしてくれてもいいのでは?」と思ったことは事実ですし、少なくとも通知の頻度を選べたほうが良いのではと感じました。
ところが、数日使い続けてみると、このくらいの控えめさがちょうど良いと思えるようになってきました。
仕事が忙しい日などは、頻繁な通知は煩わしくなるものです。あまりガツガツとサジェストされるよりも、普段は淡々とモニタリングが続けられ、ふと思いついたときにアプリを立ち上げて心身の状態を確認したり、少し疲れが溜まったと感じたときにリカバリーに関する助言を得たりするという使い方が、次第に心地よく感じるようになりました。
一週間試しただけでしたが、このような使い方でも良質な睡眠につながる生活を意識するようになり、最後の方にはリカバリー率も少し改善させることができました。
厳しいパーソナルトレーナーではなく、忙しい日々にそっと寄り添ってくれるメンターを求める人には、ちょうど良いヘルスケアデバイスと言えるでしょう。
あわせて読みたい
-

- 「起きたいんだけどね」飼い主を起こしたいんだかそうじゃないんだか分からない猫
- 起きたいんだけどね / (C)のべ子/KADOKAWA世界に飛び出たあずきさんは止まらない!国内外問わず、グロ…
- (レタスクラブニュース)[LOHAS,スローライフ,健康]
-

- モトローラの現行スマホ「moto g05」、2万円でお釣りが来るって知ってた?
- モトローラの現行スマホ「moto g05」、2万円でお釣りが来るって知ってた?Image:Amazon.co.jp こちらは「か…
- (Gizmodo Japan)[ダイエット]
-

- UGREENの“6ポート最終形態”でPCもスマホも爆速充電。驚異の63%OFF中 #Amazonセール
- UGREENの“6ポート最終形態”でPCもスマホも爆速充電。驚異の63%OFF中 #AmazonセールImage:Amazon.co.jp こ…
- (Gizmodo Japan)[カフェ・スイーツ]
-

- 昭和レトロを旅の思い出に!旅先の夜を楽しむ「ニュー・ウエダ」の「ナイトパスポート」とは?
- 長野県の東部に位置する上田市では、知られざる街のディープな魅力を“上田市のB面”として紹介するプロモー…
- (Walkerplus)[アウトドアグッズ]
-

- 上質なデザインと機能性が融合!【セイコー】の腕時計で格上げする毎日の時間管理!Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[気象]
-

- アップル、本気でスマートグラスを作る? 新型チップを開発中か
- アップルが「スマートグラス(スマートメガネ)」向けの新型チップを開発していると、ブルームバーグが報…
- (GetNavi web)[GetNavi web]
キーワードからさがす
(C)ONE PUBLISHING