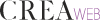「ふたをして煮る」ときは“穴のない”ふたで!…NHK「きょうの料理」出演の人気料理研究家が明かす〈レシピに掲載されないおいしさのヒミツ〉
NHK「きょうの料理」や「あさイチ」など、テレビでも活躍中の人気料理研究家、井原裕子さん。最新刊はレシピだけの本ではなく、たっぷりのエッセイ+レシピという構成だ。「料理研究家として、ずっと書けなかったこと」をたくさんつめ込んでいるという。その思いと、これまでのことを伺った。

「レシピは短くすっきり」が基本。でも「おいしく作る」ためにもっと書き込みたい

――タイトルに「レシピに書けないおいしいのコツ」とありますが、「書けない」理由とは一体……?
井原裕子さん(以下、井原) まずシンプルに、文字数の問題です。料理雑誌や料理本は「なるべくレシピは短くすっきり」が基本。長いと「むずかしそう」と思って読み飛ばされてしまうんですね。でもおいしく、失敗なく作るためには、伝えたいことはやっぱりいろいろあります。
「ほうれん草をゆでる」を例にしてみますね。レシピだと「ほうれん草をゆでておく」で終わってしまいますが、おいしく作るなら「少量ずつゆでる」と私は書きたい。一気に1束入れると、お湯の温度が下がって、また煮立つまでに時間がかかります。そうするとゆで加減にムラができて、ぐにゃっとしてるところもあれば、そうでないところもあり、食感が悪くなるの。
ほうれん草1束なら、私は3回に分けてゆでます。下ごしらえひとつで味の差ってかなり出てしまうんですよ。でもここまでレシピに書き込むのは実際問題むずかしい。
――本の中ではほうれん草はグラタンのレシピに出てきますね。「フライパンでゆでる」と指定がありました。
井原 青菜をゆでるなら、少し深さのあるフライパンが便利なんです。すぐにお湯が沸くし、ほうれん草も切らずにそのままゆでやすいから。ブロッコリーもね、小房に分けたら、少量の水と一緒にフライパンに入れて、ふたをして蒸しゆでにするのがおすすめ。ほどよいかたさにゆでやすく、ブロッコリー独特の青くささも飛ぶ。時間もかからないうえ、栄養も逃げない。でも、通常のレシピだと「ブロッコリーをゆでておく」となってしまいますね。
――すっきりレシピは読みやすいけど、その「行間」に様々なコツが省かれているわけですか。
井原 編集部からの「できるかぎり、レシピは3工程まで」という要望は多いんです。それ以上長いからって掲載されないことはないけど、文章は可能なかぎり短くカットされてしまうでしょうね。
ページ数は限られていますから、レシピがはしょられるのは仕方ない。ただ「おいしく作る」なら、あるいは「失敗しないように作る」なら、もっともっと書き込みたいんですよ。そして「なぜそうするのか」も。理由が分かるとちょっと面倒でも「やろうか」って気持ちになれるでしょう?

「ふたをして煮る」ではなく「穴のないふたをして煮る」と書きたい
――「はじめに」にあるフライパンのふたの「穴」の話は納得でした。
井原 「ふたをして○分煮る」というとき、ふたに穴があるとないでは仕上がりがまったく違ってしまうんです。私は必ず「穴のないふた」を使ってほしい。例として麻婆豆腐を挙げますが、日本の家庭料理における麻婆豆腐って、香味野菜とひき肉を炒めて煮て、それぞれのおいしさが溶け出たスープを味わう料理だと思っています。そのスープにとろみをつけて、豆腐と味わう。

――なのに穴のあるふたで煮ると……
井原 水分がどんどん飛んで、おいしいスープを味わえない。なんてもったいない! だからこそ「穴のないふたをして○分煮る」と書きたい。私の記事なら、注釈で入れてもらいますけどね。だからレシピってしっかりと読んでほしいんですよ、さらにいえば火加減のことも。
――と、いいますと?
井原 「火にかけて、沸騰したら中火にして○分煮る」という表現もレシピではよく出てきます。これ、全体を一度ぐつぐつと沸かすのが大事なんです。そうなってから火を弱めて「ふつふつ」ぐらいの状態にして、煮ていく。ちょっと沸いたぐらいで火を弱めると、全体の温度が上がってないから素材から味が出てこないし、そもそも「煮る」という調理になりません。
ガス火の場合は、最初に鍋のふちのほうから沸いてきます。そして最終的に真ん中もぐつぐつしてくる。こうなって、全体が沸いたことになるんです。ちなみにIHは逆で、真ん中から沸いてきて、熱が外側に広がる。どちらにせよ、全体がぐつぐつと煮えてから、火を弱めて煮ないと、おいしく仕上がらない。
――火を弱めないで、ぐつぐつのまま煮てはいけませんか。
井原 そうすると雑味が出てきて、やっぱりおいしくならない。大事なことですが、文字数的にはここまで書き込めません。
――「ぐつぐつ」とか「ふつふつ」という煮加減の言葉って、文字で伝えるのは微妙な感じでもありますね。
井原 一緒に作って煮汁の状態を見てもらえれば、一発なんですけどね。動画だと伝えやすい部分です。
私は「DELISH KITCHEN」という料理動画メディアの料理監修とレシピ指導を6年ほどやっていたのですが、利用者の方々から「失敗したくない」という思いをとても強く感じました。だからなるべくリスクのないよう詳しく伝えたくて。でも書き切れない事情も理解しています。ジレンマですね。
――だから今回の本で、思いっきり書き込まれたと。文字量以外で「レシピに書けない」理由もあるのでしょうか。
井原 現代はやっぱり時短レシピが中心で、「作り始めから完成まで20分以内」という要望が多いんです。私も子育てしながら働いていた時期は時短料理のお世話になりましたし、ニーズも分かる。でも料理研究家としては、じっくり時間をかけて作るおいしさも伝えたい。また料理雑誌だと、ごく一般的な食材や調味料しか使えないんです。薄口醤油でもNGになることもあるんですよ。
――本の中ではカリフラワーやビーツ、バルサミコ酢やバジルペーストの意外な活用法や、じっくり料理として牛すね肉を使ったもの、グラタンなども紹介されていますね。

井原 「あ、こんな使い方もできるんだ!」と思っていただけたらうれしいですね。他にも「切る」だけじゃなく、こんな食材はちぎって調理してもおいしいとか、もやしは揚げてもおいしいとか、しょうが焼きは鶏むね肉でやってもおしいですよ、なんてことも。
あと私は貧血にずいぶん悩まされてきたんですが、鉄分の豊富な食材として「なまり節」が激推し! でもちょっとマイナーな存在らしく、なかなか伝えられる機会がなくて。おいしく食べるレシピを紹介しています。いろんな理由から「書けない」ことを、この本にはたくさん詰め込みました。
――今まで溜めてた思いを書かれて、ストレス解消にもなったのでは?
井原 「書けない」のは残念ではあるけれど、不満ではないんです。自分の仕事って、基本的に「日本の家庭における一般的な調理道具と調味料で、どこでも買いやすい食材で作れる、おいしいレシピを考案すること」だと思っていますから。この本は「もっとあれこれ、じっくり料理してみたい」「もっと料理上手になりたい」と思っている方に届くといいな、って思っています。
48歳で独立、実は波乱万丈! 井原裕子さんのこれまでのこと

――小さい頃から料理好きだったんですか。
井原 母がお菓子作りの大好きな人で、伯母たちもすごく料理上手で。小さい頃からおいしいものに囲まれて、自然と料理好きに育ちました。愛知県出身なんですが、かたい八丁味噌をすり鉢でだしと合わせておくのは私の係。梅干しやらっきょう作りなども伯母に教えてもらって。昔ながらの日本の家庭料理を経験できたのは、幸せだったと思います。
――海外でもこれまで、計8年ほど過ごされたそうですね。
井原 夫の赴任に伴ってアメリカのヒューストンと、イギリスのロンドンで暮らしました。それぞれを拠点にあちこち旅もして、ヨーロッパはほぼ全域旅したでしょうか。現地の食材と調味料でいろいろ料理できたのは楽しかった。地元の方のホームパーティに呼ばれてみんなで料理したり、ヒューストンってメキシコや南米の方も多いから、そういう料理にも触れられたり。
――各地で料理教室にもよく行かれたとか。
井原 はい、そのときとったノートは今も大事にしています。イギリスで通ったイタリア料理教室はね、主宰の方がカルチャークラブってバンドのドラマーの奥さんで、料理上手でかわいいイタリア人でした。ロンドンの家のお隣さんはインドの方。いい匂いが漂ってくるものだから、何度か料理を教えてもらいましたよ。
――帰国されて、36歳から料理研究家の大庭英子さんのアシスタントになられますが、これはどういうきっかけで?
井原 本当に偶然、私が料理好きだと知ってる知人が「大庭さんが探しているんだけど、どう?」と声をかけてくれたんですよ。子どもも大きくなっていたタイミングだったので、「やりたい!」と。でも独立する気持ちは当時、全然なかったんです。
――どのくらいの頻度で行かれてたんですか。
井原 当時から先生は大人気で、お仕事の依頼が毎月たくさんありました。だから平日はずっとアシスタント仕事。勉強になりましたね。12年ほどさせていただきましたが、季節ごとの料理を毎年間近で拝見できたし、食材の選び方から教えていただけて。この期間は人生の宝物です。
――2006年には、離婚も経験されます。
井原 はい。いろんな理由があったけれど、お互いの思う「家族の形」が違いました。私はお互いに働いて一緒に子育てして家族を作っていきたかったけれど、向こうはそうではなかった。平等な感じがしなかったんです。
――夫婦間が対等な関係ではなかった……?
井原 子どもができてから、そういう感じがずっとあって。生きづらさを感じていました。子どもがある程度大きくなったとき、仕事をしようと思ったら否定的な答えが返ってきたの。元夫は、私の人生なんてまるで考えていなくて、「自分の人生=私の人生」だと思っていた。
――「俺に付いてくればいいんだ」的な。
井原 人の後ろを歩くってつらいですよ。先が見えないし、自分で何も決められない。レールが1本しかないことに耐えられず、2年かけて離婚しました。
――その後に料理研究家として独立されます。12年間アシスタントとして修業されて、先生から「井原さん、もうそろそろいいんじゃない?」と背中を押されたと。

井原 そうなんです、48歳から第2の人生。一般的には仕事において地位を確立する年齢で独立しました。しばらくは当然仕事もありませんから、貯蓄を切り崩す日々。同業で活躍されている人の多くは年下の方ですので、正直引け目を感じたり、先行きに不安を感じたりも勿論ありましたよ。でもメンタルはまあまあ強いほうなんで(笑)、大変な時期も乗り切れましたね。
――どうやって仕事を増やしていったのですか。まだSNSもない時代、自己アピールも大変だったのでは。
井原 そうですねえ……売り込みもしましたし、一度お仕事くださった方がリピートしてくださって、少しずつ広がっていった感じです。「DELISH KITCHEN」というウェブのお仕事をしたことで、ユーザーの方々のレシピ記事に対する具体的な不満と要望をダイレクトに知れたのは大きかった。そういったニーズを考えながら、自分のレシピを作っていきました。独立して5〜6年後にはどうやら仕事も増えてきて、別れた夫の年収を超えたときは本当にうれしくて(笑)。ちょっと自信持っていいかなと思えたときですね。
――井原さんは料理研究家としての自分の「武器」って、何だと思われていますか。
井原 「引き出し」はそれなりに多い方だと思うんです。両親がおいしいもの好きで、小さい頃から様々なものを食べさせてもらえました。海外では世界の料理に触れつつ、和の食材が手に入りにくい状態で日本の家庭料理も作って。大庭先生からは調理だけでなく仕事への向き合い方や人生哲学も学ばせていただいたし、「DELISH KITCHEN」では計4万点以上のレシピ指導をして、スタッフに「なぜこのレシピはこうしなくてはならないのか」を説明する、その言語化の経験は今とても役立っています。
母として子どもに料理を作りましたし、91歳になる父が食べやすい料理も作っています。人生のいろんな場面で料理してきたことが「引き出し」に入っていて、あえて言うなら、それらすべてが「武器」となってくれていますでしょうかね。
井原裕子(いはら・ゆうこ)
料理研究家、食生活アドバイザー。愛知県生まれ。大庭英子氏のもとで12年間のアシスタントをつとめた後に独立。日本の家庭料理を軸に幅広くレシピを考案、著書多数。企業向けの商品開発やフードコンサルティングも行う。
Instagram @iharayukoo
聞き手・構成 白央篤司(はくおう・あつし)
フードライター、コラムニスト。東京都生まれ。「暮らしと食」をテーマに執筆、主な著書に『にっぽんのおにぎり』(理論社)、『自炊力』(光文社新書)、『はじめての胃もたれ』(太田出版)など。
https://note.com/hakuo416/n/n77eec2eecddd/
文=白央篤司
撮影=平松市聖(人物)、豊田朋子(料理)
あわせて読みたい
-

- 福島・東浜町に「万代蔵珈琲店」 朝6時台から営業、アロマサロン併設
- 福島市のカフェ「万代蔵(まよぞう)珈琲(こーひー)店」(福島市東浜町、TEL 080-3149-2994)がオープン…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り]
-

- セサミストリートマーケット、クッキーモンスター主役のひんやりスイーツフェア開催!アイスサンドやドーナツサンデーなど
- 世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミスト…
- (Walkerplus)[スローフード]
-

- イオンモール川口のベイフローカフェが限定ドッグ販売 地元企業とコラボ
- イオンモール川口(川口市安行領根岸)内のファッションブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」のカフェで5月1…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]
-

- 高田馬場駅前F・?ビルに「サブウェイ」 27年ぶり高田馬場に出店
- サンドイッチチェーン「サブウェイ高田馬場店」(新宿区高田馬場1)が5月8日、高田馬場駅前のF・?ビル1階…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材]
-

- 料理、掃除、収納のプロも愛用!進化がスゴイ「100円」で買える暮らしの名品
- 料理、掃除、収納のプロに聞いた!100円均一で買える暮らしの名品 / 撮影/林 ひろし物価高騰であらゆるも…
- (レタスクラブニュース)[アウトドアグッズ]
-

- 無駄のないデザインが魅力!【グレゴリー】のリュックで通勤・通学もアウトドアもスマートに!Amazonで販売中!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[旅]
-

- 全国から人が集まる! 奈良の老舗カフェ&雑貨店「くるみの木」石村由起子さんに聞く、うつわへの愛と後悔しない集め方〈私物のうつわも公開〉
- 『うつわ』石村由起子/著 奥山晴日/写真 実にうつくしい本が誕生した。その名は『うつわ』(青幻舎)、…
- (CREA WEB)[地方創生]
-

- 「外房チアリーディングクラブ」が世界大会で優勝 いすみ市長へ報告
- 5月1日・2日に米フロリダ州で開催された「THE SUMMIT」で優勝を果たした競技チアリーディングクラブ「外房…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[野菜]
-

- 我が家のカーテンを切り刻んだうえ、好みのカーテンを勝手に購入し代金は我が家へ請求。義母の“嫌がらせ”の目的とは?【作者に聞いた】
- これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストー…
- (Walkerplus)[エネルギー]
-

- アーモンドミルクの味にこだわった「至福のアーモンドミルク」を味わえる限定メニューが都内2店舗でスタート!
- カフェでコーヒーや紅茶に合わせたり、料理やスイーツで使用されたりと、飲食店でも目にする機会が増えた…
- (美容最新ニュース)[健康]
-

- お気に入りのだるまを見つけたい!たかぎなおこさんの調布・深大寺ひとり遠足・前編
- へえ~深大寺でだるま市開催! / (C)たかぎなおこ/KADOKAWAこれまで数多くの国内・海外を旅するコミッ…
- (レタスクラブニュース)[東京都]
-

- 北海道で今年初めて30℃到達 沖縄・那覇も今年初の真夏日に
- 2025/05/16 15:09 ウェザーニュース今日16日(金)は沖縄や奄美、北海道で30℃以上の真夏日の所がありました…
- (ウェザーニューズ)[愛知県]
-

- 「しょうが焼きは、鶏むね肉がいい!」料理研究家・井原裕子さん考案のヘルシーレシピ<ひと手間で味が格段においしくなる工夫も>
- 料理動画メディア「DELISH KITCHEN」監修のほか、テレビや書籍でも活躍する人気料理研究家、井原裕子さん…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
-

- NEWS小山慶一郎「わかんないっす…」からの 華麗な千切り!姉みきママの爆上げ指導
- トルコのベリーダンスをイメージした華麗なポーズでキメ! / 調理/みきママ 撮影/福井麻衣子 スタイリン…
- (レタスクラブニュース)[レシピ]
-

- 【結果発表】「贈りもの大賞2025」大激戦の【グルメ部門】ベスト5には、端正な和菓子やホテルメイドの洋菓子、肉ギフトがランクイン!
- 毎年大激戦の【グルメ部門】。今回の第1位は!? 2007年9月号に初めて登場し、17年以上、好評を博してきたCR…
- (CREA WEB)[ホームパーティ]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.