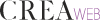【怪談】深夜のファミレスに現れた“もう一人の客”……ガラス窓の向こうで女が呟いた戦慄の一言とは一体……。

生配信サービス「TwitCasting」で、2016年から実に9年もの間新たな怖い話を生み出し続けている怪談チャンネル「禍話(まがばなし)」。ネット上でファンが文字に書き起こす“リライトブーム”を引き起こしたほか、2021年にはドラマ化もされ、近年は漫画版や人気ホラー作家・梨さんとのコラボ小説も発売するなど、その人気は衰えを知りません。
北九州の書店員である語り手のかぁなっきさんと、その後輩の映画ライター・加藤よしきさんが語る怪談から、今回は“深夜のファミレス”にまつわるお話をご紹介――。
ふと目にした駐車場に見えたもの

「そんなものですかねぇ」
「そんなものじゃない。勝手に入るのはダメだけどさ、ウチとしてはこうやって帰りに一息つきに寄ってくれるから儲けものだよ」
「はぁ……まあ」
ピンポーン。
「すみません、注文いいですかぁ〜」
「今伺います!」
食べ物の注文を受け、出来上がったフライドポテト、唐揚げ、パフェという大学生らしいとりとめもないメニューを給仕し終えると、再び時間がゆっくりと流れ始めました。
Tさんがわいわいと盛り上がる彼らをぼーっと見つめていると、ふいに、ポンとOさんに肩を叩かれました。
「ほい、暇ならフロアのモップでもかけて」
「え〜、Oさんはやらないんですか?」
「俺は夕方にやったからね。あと、俺までモップかけたら誰が接客するの。ほら、早く」
「もうお客さんなんか来ないですよ……」
そう愚痴りながら、Tさんは店内のモップがけを始めました。
「失礼しま〜す」

ちらりとこちらを見てぺこりとお辞儀をする女の子。パフェをパクつくもう1人の女の子。そして、彼女に廃墟の幽霊の考察を熱っぽく語る2人の先輩たち。
『ああいう廃墟って、雰囲気があれば怖い事実がなかったとしても皆寄って来るし、いつの間にか怖い噂ができちゃうものなんだよ』
幽霊の正体見たり枯れ尾花。
そんなことわざを聞いたことがあるけど、人は見たいものを見てしまう生き物なのかもしれないなぁ……——さっきのOさんの言葉を思い返して手が止まるTさん。
「どうかしました?」
先ほどお辞儀をくれた子にそう言われ、「あ、いえ、すみません」とひとつ先のボックス席までモップをかけながら移動したとき、ふと目線が駐車場の方に向きました。
Tさんが駐車場に目を向けると……

駐車場の照明ポールに照らされた、どこにでもありそうな黒いコンパクトカー。
その助手席に人が乗っていたのです。
あれ、1人残っていたのかな……。
確かめるように目をこらすと、黒い髪の毛をした、白っぽい服を着た女と思しき人影がじっと前を向いて座っていました。
「病院ってことはそこで亡くなる人は定期的に出るわけで、それが毎回怖いお化けになるものですかねぇ〜……」
「だから、何か違法な治療していたとか、そう言うことじゃない?」
「違法な治療って……リアリティねぇこと言うなぁ」
「ですよねぇ〜」
大学生たちが車に誰か残してきているようには見えませんでした。
急に恐ろしくなったTさんは、目線を床に下げてそそくさとOさんのいる待機場所に引き上げたそうです。
「モップ終わりました」
「ちゃんとかけただろうなぁ〜」
「はい」
「……どうしたの?」
「あの、先輩……駐車場の車に、誰か乗っていません?」
「駐車場?」
Oさんは少しフロアに身を乗り出しながら目を凝らしました。
「……あ、確かに誰か座っている」
「そうなんですよ。こんなこと言うとあれかもしれないですけど、おかしくないですか?」
「……え、あれ、病院着か?」
「えっ」
思わず振り返ったTさん。Oさんと同じように目をこらすと、確かに女の着ている服は妙に薄っぺらで、外に出るときに着るような服には見えませんでした。
「……ちょっと聞いてみるか」
「え、先輩!」
戸惑って後を追うTさんをよそに、Oさんは4人組のお客さんの方へ歩いていってしまいました。
「あの、お客様ちょっとよろしいでしょうか」
「え、はい。なんですか?」
「つかぬ事をお聞きするのですが、お客様は4名様でよろしかったでしょうか?」
「……は? 4人ですけど」
「あの、駐車場の方にもう1人お連れ様が——」
「キャアアア! 先輩あれ!!」
Oさんの言葉を遮るように視線を駐車場に向けた女の子の1人が悲鳴をあげ、その場にいた全員が彼女と同じ方向を見ました。
「誰……あれ」

あの女がいつの間にか車の脇に立ち、こちらを見ていました。
ニコニコと笑い、何やらパクパクと口を動かし、薄っぺらな病院着を着て、裸足のまま。
「誰……あれ」
ペタ。
「え?」
ペタペタ。
「ちょっ、ちょっ、え? え?」
ペタペタペタペタペタ。
その女は張り付いたような笑顔で口元を動かしたまま、こちらに向かってコンクリートの上を素足で走ってきたのです。
バン!
あっという間にボックス席の窓ガラスに両手を掲げて張り付いた女。
皆、後ずさりした姿勢のまま身動きできずにいたそうです。
女の右手がもぞもぞと動き出すと、手にはボロボロに汚れたガラケーが握られていました。女は口をパクパクと開き、何かを言っているようでしたがその声は全く聞こえません。
女はゆっくりと番号キーを押し始めるも、かすかに見えるガラケーの画面は真っ黒で、まるで電源が切れているようでした。
トゥルルルルル! 鳴り止まない電話

トゥルルルルル!! トゥルルルルル!!
レジにあったお店の電話が鳴りました。
トゥルルルルル!! トゥルルルルル!!
トゥルルルルル!! トゥルルルルル!!
鳴り止まない電話。
無視できない状況にOさんがおずおずとレジに向かうと、女の方を見つめたままゆっくりと受話器を取ったそうです。
「はい、もしもし…………う、うわぁぁぁ!!」
Oさんが突然受話器を投げ捨て、レジ上の小物を引き倒しながらその場に尻餅をつきました。
「おーい、何を騒いでいるの〜?」
キッチンの奥から社員さんの心配する声が聞こえましたが、Oさんは茫然自失としていたそうです。
「うわっ!! おいっ!!」
ふいに男子学生の一人が窓を向いて叫んだのでそちらを見ると、あの女は忽然と姿を消していました。
ドタバタと席から離れてOさんの方に駆け寄る一同。
「だ、大丈夫っすか、お兄さん……」
「Oさん、どうしたんですか……?」
「行けないって……」
「はい?」
「『私、人がいっぱいいるところは嫌いだから、行けないんです』って。あと、『あ、そうそう、病院着ってこんな感じで良かったですよねぇ?』って言ってた」
◆◆◆
結局、大学生のお客さんたちは日が昇るまで、窓から離れた席に移動してお店に留まり続け、TとOさんは朝日の中、血の気の引いた表情で車に乗り込む彼らの背中を見送ったそうです。
それ以降あの女が店に現れることはありませんでしたが、しばらくしてTさんはそのバイトを辞めたそうです。
文=むくろ幽介
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.