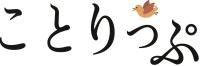京都・伏見の型染め専門工房「馬場染工場」で、型染め体験のワークショップを♪

伝統技法により職人が一枚一枚手作業で型染めを行ない、110年にわたって上質な風呂敷をつくりつづけてきた「馬場染工場(ばんばせんこうじょう)」。2024年11月にオープンしたギャラリー&ショップでは、伝統柄からモダン柄まで多彩なデザインの風呂敷を販売するほか、風呂敷の型染めが体験できるワークショップも開催。京都のきもの文化を支えてきた職人技にふれてみませんか。
京阪本線の伏見稲荷駅から、伏見稲荷大社の鳥居とは反対の西側へ。15分ほど歩くと屋根に一文字瓦を整然と冠した趣ある木造合掌造りの建物が見えてきます。こちらが1913(大正2)年創業の型染め工房「馬場染工場(ばんばせんこうじょう)」。工場に隣接するスタイリッシュな建物がギャラリー&ショップです。
ギャラリー&ショップで扱う風呂敷のデザインは、伝統文様、着物の古典柄をアレンジしたもの、Marble.coが手がけたものなど全30~40種。お弁当を包んだり、贈りものを包んだり、インナーバッグとして使ったり、旅行時に着替えを包んだり、と工夫次第でさまざまに活用できるのが魅力の風呂敷。コンパクトに折りたたむことができるので、一枚持っておくと重宝します。欧米では、ビニールや発砲スチロールなど梱包材の代わりに何度も使える風呂敷の人気が高まっているのだとか。
「型染め」とは、文字通り型を使って染色すること。染料をつくる「色合わせ」、染色台に生地を貼る「地貼り」、生地に染料をのせる「捺染(なっせん)」、生地に染料を定着させる「蒸し」のほか、「洗い」、「湯のし」「端縫い」というさまざまな工程を経て、一枚の染めものが出来上がります。馬場染工場が創業以来手がける京都北部の絹織物「丹後ちりめん」を使った型染めの技術は、世界的に有名なハイブランドも信頼を寄せるほどです。
ワークショップでは、型染めの工程のなかでも象徴的な「捺染」を体験します。染色用の台紙は、職人の手彫りによる「伊勢型紙」を使用。古くから着物に図柄を染める際の型紙として使われてきた染色用具です。刷毛も実際に職人が使っているのと同じものを使います。
はじめに、壁に飾られた風呂敷のなかから好きな図柄とサイズ(45cm・70cm・90cm)を選びます。つづいて伊勢型紙のアルファベットや数字を選んだら、刷毛に顔料を染み込ませ、くるくると円を描くようにこすります。
顔料をつけすぎると輪郭がにじんでしまうので、微調整します。むらなくきれいに色がのるよう、力加減も難しいところ。
予約時に希望すれば、木造合掌造りの工場で作業風景を見学することもできます。この日は手ぬぐいの型染めを見学。全長27mもの染色台の上にピシッと生地を貼り、細かな網状になった染型を使って色をのせていきます。一日で手ぬぐいなら1000枚、風呂敷なら500~600枚分の染色を行なうのだそうです。
時代を超え、京都の文化を支えてきた伝統技術を間近に見て、ふれて、体感して。世界にひとつだけの風呂敷をつくってみませんか。
あわせて読みたい
-

- お弁当で食中毒に!? 避けるべき意外なおかず・調理法【管理栄養士が解説】
- 【管理栄養士が解説】夏は雑菌が増えやすく、お弁当の食中毒リスクも高くなります。避けるべきおかずや調…
- (All About)[お弁当]
-

- 京都・吉田山の青もみじさんぽ、新緑に輝く神楽岡から京大キャンパスへ♪ 隠れ家カフェや庭園美術館も
- 桜の花びらが舞い散ると、次にやってくるのが青もみじの季節。銀閣寺近くの吉田山は一帯が吉田神社の境内…
- (ことりっぷ)[芸術,ことりっぷ]
-

- 有休は権利なのに「私用じゃ認められない」と言われた…“取得しにくい風潮”はなぜいまだにあるの?
- 会社で働く人の権利である「有休」ですが、そこにはさまざまな“モヤモヤ”が横たわっているようです。今回…
- (All About)[旅]
-

- 【富山県 〜春の絶景・風物詩10選〜】奇跡のような“春の四重奏”は、ここでしか出会えない/2025年版
- 日本が誇る四季折々の魅力に迫る季節の絶景特集。まだ知られざる四季折々の表情を見せてくれる日本の風景…
- (CREA WEB)[白川郷]
キーワードからさがす
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.
Copyright (c) 1996- 2025 Shobunsha Publications All Rights Reserved.