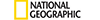【動画】ホエザルの子をさらうオマキザル、奇妙すぎる行動が拡大

中米パナマの沖にあるヒカロンという小さな島で、ノドジロオマキザル(Cebus capucinus imitator)のあるオスが、穏やかならぬ行動を流行らせているようだ。顔の傷から「ジョーカー」と名付けられたこのサルと仲間のオスザルが、マントホエザル(Alouatta palliata coibensis)の赤ちゃんをさらって背中にのせているところを、自動撮影カメラがとらえていた。それまで見られたことのない奇怪な行動が、2025年5月19日付けの学術誌「Current Biology」で報告された。
「あまりに奇妙だったので、すぐにアドバイザーのオフィスに行ってこれが何なのか尋ねました」と、ドイツ、マックス・プランク動物行動学研究所とパナマにあるスミソニアン熱帯学研究所に所属する霊長類学者で、論文の筆頭著者であるゾーイ・ゴールズボロー氏は振り返る。
事態はますますおかしな展開に
このカメラは元々、島を訪れた植物学者が、石を使って食べ物を加工しているサルがいると報告したことから、2017年に設置された。
別の種のオマキザルが石を道具として使うことは以前から知られていたが、コスタリカとパナマにすむより細身のノドジロオマキザルでは、これまで確認されていなかった。しかしカメラを設置したことで、実際に平らな面の上で石を使って種子や果物、さらにはカニやカタツムリまでも割っている様子が撮影された。
赤ちゃんをさらう行動が初めて撮影されたのは2022年1月26日だった。カメラには、若いオスのオマキザルが、ホエザルの赤ちゃんを運んでいる姿が映っていた。
翌日、同じ赤ちゃんを今度は「ジョーカー」が運んでいた。少なくとも2月3日まで、「ジョーカー」が赤ちゃんを運んでいたことが確認されている。「最初、親に捨てられた赤ちゃんを拾ったのだと思っていました」と、ゴールズボロー氏は言う。
ブラジルでは、マーモセットの赤ちゃんが別の種のサルに育てられた例が1例だけ知られている。しかしここで重要な点は、その赤ちゃんが母乳を与えられるメスに拾われたことだと、2006年にこれを報告したブラジル、サンパウロ大学のパトリシア・イザール氏は指摘する。
一方オスのオマキザルは、赤ちゃんを拾ってもどうしたらいいのかわからない。結局、赤ちゃんは餓死した可能性が高い。
さらわれた赤ちゃんは、母親から離れてしまったときに出すような鳴き声を立て、その後には何匹かおとなのホエザルが呼ぶ声も聞こえた。このことから、赤ちゃんは捨てられたのではなく、さらわれたと考えられる。
「オマキザルがどのようにして赤ちゃんを手に入れたかは撮影されていませんでした」と、マックス・プランク研究所の行動生態学者で論文の最終著者のブレンダン・バレット氏はいう。「けれどオマキザルは、束になれば自分たちよりもずっと体の大きなホエザルにもひるまないことがわかっています」
その後、事態はますますおかしな展開を見せる。
4月と5月には、別のホエザルの赤ちゃんを2匹立て続けに運んでいる「ジョーカー」が観察された。そして3匹目を引きずっている姿も見られたが、この子はすでに死んでいたようだった。別の若いオスが数匹、その後を追っていた。
9月から翌年3月までに、さらに4匹のオスザルが生きたホエザルの赤ちゃんを背中やお腹にのせていた。なかには1週間以上その行動を続けていたサルもいた。15カ月の間に、少なくとも11匹の赤ちゃんがさらわれ、そのすべて、またはほとんどが死んでしまったようだった。
次ページ:なぜ赤ちゃんをさらうのか?
なぜ赤ちゃんをさらうのか?
ブラジルでは、過去に少なくとも1度だけ、別の種のオマキザルがホエザルの子をさらった報告があった。このとき赤ちゃんは口にくわえられ、おそらく食べられたものと思われる。
しかし、ノドジロオマキザルがホエザルの子をさらう行動が記録されたのは今回が初めてだ。そして、ほかの個体がこれを真似し始めたことに、研究者たちはとりわけ強い関心を示している。
「人間以外の動物社会において、明確な適応的な恩恵がない行動が広がるという例は、極めて珍しいです。それが、今回の観察の特に興味深い点です」と、イザール氏は言う。この島には、自動撮影カメラが何年も前から設置されていたが、これまでこのような行動は一度も撮影されていなかった。ということは、これが初めての出来事か、おそらく流行の走りだろうと考えられる。
自分と同じ種の子どもを運ぶ若いオスのオマキザルが観察されることは珍しくないと、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校のスーザン・ペリー氏は言う。氏は、別の場所で数十年前からコスタリカのオマキザルを研究しているが、今回の研究には関わっていない。
「オマキザルのオスがオマキザルの子を盗もうとすることはよくあります。成功すれば、何かお宝を勝ち取ったかのように大喜びしているように見えますが、それもお腹をすかせた子どもがミルクを欲しがって鳴き出すまでです」
そうなったら子どもは捨てられてしまうことが多い。「幸い、子どもの母親やメスの親戚が近くで待ち構えていますので、子どもはすぐに助けられます」
オスの赤ちゃんが好まれる
オマキザルのオスは、オスの子を好む傾向にあると、ペリー氏は指摘する。「早いうちから親密な関係を築いた子は、成長すると協力者となり、交尾相手を見つけるために一緒に危険を冒して別の群れに移れるようになるためと考えています」
それならば、当然ホエザルの子をさらっても意味はない。しかし、子どもを運びたいという思いが強すぎて時には失敗してしまうのではないかと、ペリー氏は言う。
ゴールズボロー氏もバレット氏も同意するが、もう一つ別の傾向も関係しているのだろうとみている。ほかの個体の真似をしたいという欲求だ。「ジョーカー」は、単に子どもを運びたかっただけであり、ほかの仲間もその真似をしたかっただけなのかもしれない。
次ページ:島で退屈して不善を?
子どもを運んだからといって、そのサルの社会的地位が上がったわけではない。ホエザルの子を運んでいた若いオスは、そうしなかったオスよりも攻撃の的になっていたように見える。
しかし、入手困難だが栄養のある食べ物を手に入れるための新しい技術を学ぶことが成長にとって重要なオマキザルのような種では、仲間の真似をすれば成功することが多く、そのせいで何でも真似をしたくなってしまうのかもしれない。
退屈した動物が考えつくことは……
島という環境も要因の一つかもしれないと、研究者たちは指摘する。オマキザルの天敵が多い本土では、常に警戒して、仲間から離れないようにしていなければならない。そのため、食べ物を探すにしても時間がかかる。
対して島には食べ物が豊富にあり、脅威もほとんど存在しない。若いオスはただ単に退屈しているだけかもしれない。
「天敵がいない島にすむ動物や、安全な環境でエサも十分に与えられる動物園の動物は、新しいことを考えついたり、道具を使ったりするのがうまいことがわかっています」と、ゴールズボロー氏は言う。
多くの場合、退屈した動物が考えつくことは、役に立たず、ヒトやほかの動物を苛立たせることがあると、バレット氏は言う。「オマキザルがヤマアラシの毛づくろいをしたり、ウシのおしりを叩いたりしているのを見たことがあります。何にでもちょっかいを出し、常に世界を試し、世界と関わろうとするのです」
しかし、絶滅の危機にさらされながら子どもまでもがさらわれているヒカロン島の哀れなホエザルはどうなるのだろうか? ゴールズボロー氏は言う。
「かわいそうですが、研究者として私たちは、自然界の行動に干渉するつもりはありません。ホエザルたちがいつか適応することを願うばかりです。例えば、子どもをさらうオマキザルの群れに近づかないようにするとか。または、オマキザルの方が子どもをさらうことに飽きる可能性もあります。ホエザルの子は手が焼けますから」
あわせて読みたい
-

- イカの卵に入り込む謎の寄生虫、赤ちゃんを助ける「助産師」か
- イカの卵に入り込む謎の寄生虫、赤ちゃんを助ける「助産師」か カリフォルニアヤリイカ(Doryteuthis opal…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 原宿にアイス店「AIPAKU TOKYO」 ご当地アイスなど100種
- ご当地アイスとクラフトソフトクリーム専門店「AIPAKU TOKYO 原宿店」(渋谷区神宮前1)が6月5日、原宿に…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]
-

- 5月24日の月が教えてくれるヒント 晴れたらお出かけを
- 今日の月はWaning Moon月は欠けていく期間に入っています。新月まであと3日。 牡羊座の月の日は、インドア…
- (CREA WEB)[まち歩き]
-

- 仙台駅の「ベイクチーズタルト」リニューアル タルト以外のチーズ菓子も展開
- JR仙台駅2階在来線中央口改札内にあるチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART(ベイクチーズタルト)」仙台…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[果物]
-

- 地球から124光年離れた惑星に、生命が存在する証拠? 懐疑的な見解も
- 地球から124光年離れた惑星に、生命が存在する証拠? 懐疑的な見解もImage: A. Smith, N. Madhusudhan / U…
- (Gizmodo Japan)[植物]
-

- アースノーマット×コールマンの電池式蚊とりはアウトドアにピッタリなデザイン
- アースノーマット×コールマンの電池式蚊とりはアウトドアにピッタリなデザインImage: Amazon.co.jp この記…
- (Gizmodo Japan)[動物]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社