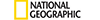韓国の海女、独自の進化を遂げた可能性、冷たい海に適応か

5月2日付けで学術誌「Cell Reports」に発表された論文によれば、韓国のチェジュ(済州)島で何世代にもわたって続いてきた海女「ヘニョ」の遺伝子を分析したところ、安全に潜水するための生理的適応が脈々と受け継がれてきた可能性が明らかになった。
ヘニョたちは一年を通してグループで海に潜り、アワビやウニなどの海産物を捕っている。水温10℃の冷たい海でも平気で潜り、海底で貝を捕って浮上する。潜水時間は比較的短いが、素潜りで1日5時間もの間、潜っては浮かび上がる作業を繰り返す。
「今でこそ、彼女たちはウェットスーツを着ていますが、1980年代までは木綿製の服で潜っていました」と論文の最終著者であるメリッサ・イラード氏は言う。氏はこの女性たちとともに研究を行っている米国ユタ大学の遺伝学者だ。
妊娠中でも潜る海の女たち
「ヘニョ」は韓国語で「海の女」を意味する。イラード氏によると、女性たちの多くは、幼いころ母親から潜水を学び、15歳あたりで本格的な訓練をはじめ、その後も生涯にわたって潜り続ける。なんと妊娠中でも潜るという。
「ヘニョは海と非常に深いつながりを持っています。海の守り人として海洋環境を大切にしています。季節によって捕る対象を変え、資源に再生の時間を与えているのです」とイラード氏は説明する。
代々女性たちに受け継がれてきた伝統だが、若い世代の関心は低い。現在の海女たちの平均年齢は70歳前後で、今の現役世代が最後の世代になる可能性がある。この遺伝的な特徴を研究できる機会も、そう長くは残されていないかもしれない。
イラード氏によれば、チェジュ島の素潜りには数千年の歴史があると考えられているが、いつから女性だけになったのかは定かではないという。
次ページ:過酷な環境に適応する人の体
過酷な環境に適応する人の体
人間の体は高地や極寒といった過酷な環境にも適応し、順応できる。
「人間は適応力が極めて高く、どんな場所でも生きていきます」と、カナダ、ブリティッシュ・コロンビア大学で心血管を研究するジョシュア・トレンブレイ氏は語る。氏は、今回の研究には関与していない。「行動や文化を変えるだけでなく、生理的にも見事に適応してきました」
フィンランドの極寒の地でトナカイを飼育する人々を研究している、米ノートルダム大学の人類学者キャラ・オコボック氏(今回の研究には関与していない)は、彼らの体で、熱をため込むことに特化した脂肪が多い傾向を突き止めた。
高地に暮らす人々の中には、空気中の酸素が比較的少ない環境に生理的かつ遺伝的に適応している人々もいると、トレンブレイ氏は語る。ただし、その適応のしかたはそれぞれ異なる。
アンデス山脈に住む人々は赤血球を増やして適応してきた。一方、チベットの人々は赤血球中のヘモグロビンの濃度を高めて適応したと考えられる。どちらの方法でも、血液中に運ばれる酸素の量を増やすことができる。
イラード氏が2018年に発表した論文によると、インドネシアの「海の遊牧民」バジャウ族は脾臓が通常より大きく、潜水中に赤血球と酸素の循環量が増えるという。この発見をきっかけに、氏は、ヘニョの体にも同じような変化が見られるのではないかと考え、10年以上にわたってヘニョを研究していた韓国ソウル大学のイ・ジュヨン氏と共同研究を行うことになった。
驚異的な潜水能力と体の変化
イラード氏のチームは、チェジュ島のヘニョ30人、同島の非ヘニョ30人、および韓国本土在住の31人のゲノムを比較した。参加者の平均年齢は65歳。全員に対し、冷水の入った桶に顔を浸けて息を止めるという疑似的な潜水実験も実施した。
実験では、ヘニョたちの心拍数が低下した程度は、他のグループの1.5倍以上だった。これによって体が必要とする酸素量が抑えられ、心臓の負担も減るため、息をより長く止められる。ただし研究チームは、この特徴はヘニョが長年にわたって積み重ねた訓練の成果だと考えている。
「心拍数の違いには目をみはるものがありました」とイラード氏は言う。「わずか15秒で、1分あたりの心拍数で40以上も低下した人もいました」
さらに、ゲノム解析の結果、チェジュ島の住民(ヘニョもそうでない人も)と韓国本土の人で明確な遺伝的違いが示された。
次ページ:変化する世界に適応するために
イラード氏によると、チェジュ島の住民は小さな祖先集団に起源を持つ可能性が高く、長い間、本土から隔離されていたとみられるという。かつて島への出入りが禁じられていた時期もあったと、イラード氏は指摘する。
チェジュ島の実験参加者の33%には、潜水によって選択を受けた2つの遺伝子変異が見られた(本土の人では7%のみ)。一方は寒さへの耐性に関連し、低体温症のリスクを下げると考えられる。もう一方は、拡張期血圧(最低血圧)の低下に関連する変異だ。
イラード氏によると、ヘニョたちは妊娠中でも潜水を続け、出産の前日まで潜る人も珍しくないという。血圧に関連するこの遺伝的変異は、そうしたヘニョの体を守っている可能性がある。研究チームは、妊婦にとって健康リスクとなる妊娠高血圧腎症などの合併症が素潜りによって悪化するのを、この変異が防いでいるのではないかと示唆している。
「冷たい水の中を潜ることは、体にとって非常に大きなストレスです」とイラード氏は説明する。「この遺伝的変異が血管に作用することで、母体と胎児のリスクを軽減する役目を果たしているかもしれないと考えています」
変化する世界に適応するために
今回の研究によって、ヘニョは潜水に適した進化を遂げたとみられる人々として、バジャウ族に次いで知られる存在になった。
「人間の多様性、進化、柔軟性を示す素晴らしい実例です」とオコボック氏は語る。
チェジュ島の住民に多く見られる遺伝的変異は、単に潜水に適しているだけでなく、チェジュ島が韓国の中で脳卒中による死亡率が最も低いという事実とも関係している可能性があると、イラード氏は指摘する。
「妊娠中でも潜り続けるたくましい女性たちが、島全体に影響を及ぼす遺伝的な特徴を実際に生み出しているとしたら、なんて素晴らしいことでしょう」とイラード氏は話す。また、氏は、この遺伝的変異の働きをさらに深く理解することが、心血管疾患の治療法の開発につながるかもしれないと付け加えた。
人間の体が過酷な環境にどのように適応するのかを探ることは、地球温暖化が進行し、氷雨を伴う嵐や熱波といった異常気象が増えるなかで、気候変動に備える上でも重要だと、オコベック氏は指摘する。
「こうした過酷な環境に人間の体がどう対応し、どれだけ状況を緩和できるかを深く理解することは、必然的に、いま私たちが直面している問題への対処につながっていくのです」
あわせて読みたい
-

- 栄養学者直伝、乾燥豆の浸し方 時短法から調理の際のコツまで
- 栄養学者直伝、乾燥豆の浸し方 時短法から調理の際のコツまで 水に浸すか、浸さないか。乾燥豆を使う料理…
- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]
-

- 海南「中野BC」が夏季限定酒「超久クールビズ」販売 お薦めは炭酸割り
- 酒造会社「中野BC」(海南市藤白)が5月13日、夏季限定商品の純米吟醸酒「超久クールビズ」の販売を始めた…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[LOHAS,スローライフ,健康]
-

- 気圧の変化による「気象病」とは?気象病チェックリストや症状が出た時の対策と予防法をご紹介
- 季節の変わり目や雨が降り出す前などに、頭痛や身体のだるさなどの不調が出る方はいませんか?症状が続く…
- (tenki.jp)[気候変動]
-

- 起業プラザひょうごで高校生向けイベント「ビジネスアイデア作成道場」
- 高校生向けのビジネスアイデア作成支援イベント「ビジネスアイデア作成道場」が6月1日、「起業プラザひょ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[気象]
-

- 今が絶好のタイミング? 酷暑対策に効果的なグリーンカーテンの作り方
- 2025/05/11 05:00 ウェザーニュース今年の4月は寒の戻りが話題となりましたが、平均気温としては平年より…
- (ウェザーニューズ)[地球温暖化]
キーワードからさがす
(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社