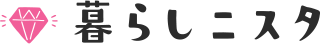すごくやさしかったり、急に怒り出したり…。定型発達の人にはわからない〈ネガティブな気分屋〉の裏にある感情って?【もしかして…発達障害!?】
「決めたルールをすぐ変えてしまう」「言い返されるとイライラする」。これがいつものこととなると、発達障害の傾向がありそうです。
「昨日と言ってることが違う」一貫性がないので、子どもを不安にさせてしまいます。【ADHD傾向】

Dさん(42歳)は、小学2年生の子どもに「宿題をいっしょにやろう」と提案。機嫌がよかった昨日はうまくいき、親子関係も上々でした。翌日、子どもはお母さんとまた宿題をやりたいと張り切って帰ってきたのに、疲れていたDさんは「自分でやりなさい」と突き放してしまいます。
「宿題をいっしょにやる」という根気のいる作業がめんどうだと感じてしまったのかもしれません。これが、ADHDのお母さんの困ったクセ。子育てでつまずきがちな、「態度が一貫していない」という特性です。
子育てでは一貫性、継続性がとても大切。そうでないと子どもは安心して暮らすことができないからです。
Dさんはゲームに関するルールもコロコロ変えてしまいます。昨日は「1時間ならOK」と言ったのに、翌日は禁止。気まぐれな対応をされて、子どもは混乱してしまいます。これでは子どもとの信頼関係がうまく築けません。
さらに、感情的に反応しやすい性質もあるため、子どもの反抗的な態度にムカッとして大きな声を出してしまうこともあるかもしれません。思春期になって子どもが手ごわい反応をするようになると、親子ゲンカが増えるケースも。
わが家のルールを決めたら、紙に書いて見えるところに貼るといい
安定した子育てをするためには、毎日のルーティンづくりが重要。まずは、毎日やることと時間の目安を書き出してみましょう。
まず最初に食事と寝る時間を決めると、「食事時間を守るため、ここで買い物に行く」とか、「ここで調理をスタートする」というように自然に流れができてくるでしょう。
すると、宿題を始める時間、お風呂と寝る時間もうまく定まっていき、だんだんとルーティンをつくっていくことができます。
また、重要なのは「方針がブレないこと」「態度をコロコロ変えないこと」。ゲームやおこづかいなど、ルールを決めたら、子どもといっしょに確認して、それを紙に書いて貼っておくといいですね。
それを変えるときは、必ず家族で話し合いを。子どもが混乱しないように、一度決めたことを簡単に変えないことが大事です。
▶次の話 「やるって言ったよね…?」。定型発達の人にはわからない〈仕事が遅い人・できない人〉の脳内で起きていること【もしかして…発達障害!?】
キャリア約30年の精神科医が
発達障害による「生きづらさ」
の対策を徹底レクチャー!
部屋が片づけられない、約束の日時を間違える、集団から孤立しがち…など、あるあるな発達障害傾向と「ラクに生活するための考え方や生活のヒント」を伝授。「もしかして発達障害!?」の夫や子ども、仕事関係の人の理解にもつながる1冊です!

『もしかして発達障害?「うまくいかない」がラクになる』1,760円/主婦の友社 司馬理英子著
Amazonで詳しく見る 楽天で詳しく見るキーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.