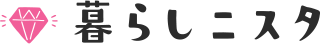夜になるとヘトヘトで、夫の戯言など、真に受けている余裕もなかった。|うさぎの耳〈第九話〉谷村志穂耳〈第九話〉谷村志穂
◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉
学生の頃から、ここは、馬術部では皆が憧れた町だった。ファームが点在し、名だたる競走馬たちを育てている町。特に、このファームは前進の頃から、離乳直後の馬たちを競走馬に育成していくための、中期育成牧場で知られていた。馬の小学校とも呼ばれていたはずだ。
「同じ学校でもさ、馬の学校だったら、楽しいんだろうなとか思っちゃうんですよね、私は」
と、冗談めかして隆也が口にした言葉を、今頃になって思い出していた。
理玖が生まれたばかりで、こちらは毎日、夜になるとヘトヘトで、仕事から戻った隆也の戯言など、真に受けている余裕もなかった。本当にそんな望みがあったのなら、ちゃんと言ってくれたらよかったではないか。
見事な、放牧地。
緑の草が一面に広がり、馬たちが光を浴びている。人間はその陰になって、彼らを育み、支える役に徹するのだろう。自分が陰でいられる場所。
穏やかな風が吹いていた。
夫は、逃げた、のではなかったのだ。彼にとっての楽園に飛び込んでいたのだ。
大好きな馬たちを日がな眺めている。
さぞ満足しているだろう。
でも、なぜ、たったひとりの息子ではいけなかったの?光の中に眺むるのは、馬たちでなければいけなかったの?なぜ、家族と一緒には飛び込めなかったの?今更訊いても仕方のない言葉を飲み込む。大きな空が、迫ってくるようだった。なんて美しい、大きな空。余計に泣きたくなった。
「あの、観光の方でしょうか?」
不意に声をかけられ、振り返ると、ファームの名が印刷された紺色のポロシャツに、キャップを被った眼鏡の女性が立っていた。
首を横に振ってしまう。
「そうではないです」
女性が、少し驚いた目をこちらに向けたから、よほど口調が強かったようだ。
「でしたら、ご用件はなんでしょうか?ここ、一応、観光の人たちは受け付けていないものですから」
観光なんかであるものか。そんな悠長なことが、今の自分に、できるはずがなかった。
「動物に病気の心配とかもあるので」
黙っていると、少しきつい口調に変わった。
斜め掛けにしてきたポーチから、写真を取り出す。
「この人を、探しています」
朝の光の中で、隆也がコーヒーカップを手に写っている貴重な写真。そしてもう一葉は、生まれたての理玖を抱いている写真だ。
彼女は、軍手を外してズボンの後ろポケットに収めると、写真を手に取った。眼鏡のフレームの中央に手をやった。女性の瞳が揺れていたのがわかった。
「夫なんです。ここで働いているのを見たという人がいて来ました」
彼女は写真を、押し戻し、少し、声を詰まらせた。
「その人は、そうですね、どうなんだろう」
不思議な返事だった。
「いるんですね?連れてきてもらえませんか?」
「どうかな。私にも、わからない」
そう言うと彼女は、踵を返した。グレーの長靴を履いた足が、やがて放牧地の奥にある、厩舎へと向かって駆け出した。しばらくすると、そこから作業服を着た人たちが、複数ぞろぞろ出てきた。固唾を飲んで見渡した。だが、その中には隆也の姿は見当たらないようだった。
自分の鼓動が、内側を通じて再び大きく響いてくるのが聞こえるほどだった。
「あなたの顔を見たら、逃げ出すかもしれないよ」
M駅でそう言った、莉子の声を思い出す。ベビーカーの中の理玖はぐずって、手足をばたつかせ、こちらにその丸い手を伸ばしてきたのだ。
同じユニフォームを着た厩舎の人たちが、複数こちらを見ていた。一人だけ、年配の男性がスコップを置いて、こちらに向かって歩いてきた。
「なんでした?うちのファームに、お宅の旦那さんがいるとかって聞きましたけど」
「写真を見ていただけますか?」
もう一度バッグから取り出そうとするのに、男はそれをチラと見ただけで、手で制した。
「悪いけど、ここにはそういう人はいないですよ」
▶次の話 夫はここで、誰か女性の世話になって、生きているのかもしれない。|うさぎの耳〈第九話〉谷村志穂耳〈第九話〉谷村志穂
◀前の話 「今すぐ、ここに来なさいよ!」叫んでやりたいのに、立ち尽くしてしまう|うさぎの耳〈第九話〉谷村志穂

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。
あわせて読みたい
-

- 成増に米粉生地で作るクレープ店「ちゃみるすたー」 イートインも
- 米粉生地で作るクレープ店「Chamillstarrr(ちゃみるすたー)」(板橋区成増2)が4月18日にオープンした。…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ]
-

- 大洗に朝ごはん専門店 「普段」をつくる商店街の「台所」に
- 朝食専門店「台所」が4月15日、大洗町磯浜町にオープンして1カ月がたつ。(水戸経済新聞) メニューはご飯…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[観光,旅]
-

- 和歌山城公園で「お城の動物園応援フェス」 収益の一部を寄付
- アート&音楽イベント「わかやまお城の動物園応援フェス」が5月31日・6月1日、和歌山城公園(和歌山市一番…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[動物]
-

- 北広島・エスコンFに「ミスターチーズケーキ」 ファイターズコラボも
- チーズケーキブランド「Mr. CHEESECAKE(ミスターチーズケーキ)」のポップアップストアが5月30日、エスコ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[北海道]
-
- あの日の"選択"は間違いじゃなかった!交際スタートからまさかの…!?【40歳からのオトナ婚#20】
- 40歳を過ぎてから結婚した女性たちには、どんな"ヒミツ"があったのか…? 「東大合格より難しい」と…
- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.