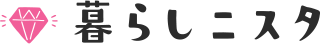母でも妻でもなく、ずっと待っている一人の人間|うさぎの耳〈第八話〉谷村志穂
◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉
こんな風に言ってもらえる仲間意識なんて、もうとっくに忘れていたはずだった。馬術部同士で結婚したのに、理玖が生まれて、最初に同窓会の誘いがあった時に、行きたくないと言ったのは、隆也ではなく自分の方だった。そんな隆也さえいなくなった後は、世の中のすべてに距離を置いていた。世間から身を隠すように生きるのが理玖と自分のためだと考えていた。莉子と出会ってはじめて、扉が開いた。自分の中にはまだ、人恋しさがある、と。だとしたら、やっぱり、会いたい人がいる、と。心の奥底に、ずっと隆也を待っている一人の人間、母でも妻でもなく、隆也と出会った頃の私がいる。せめて訊いてみたいのだ。どうして、私たち母子の前から、何も言わずに居なくなったの?
「さあ、次行こうよ」
白坂の声が響いた。
二人は、もし高知の男が異なっていたら、その日のうちに広島へと移動する行程を組んでいた。
高知駅でレンタカーを返し、特急列車で岡山まで。岡山からは新幹線で広島へ向かうという行程だ。そこにいる塾講師は、夜、子どもたちに英語を教えている。
週末の休日内の一泊二日で、なんとか両方回れるように、二人が組んでくれた旅程。
地図を想像しながら、夕方まで連絡を待つことにした。
白とオレンジの毛糸玉を手に取り、パペットの胴体を編み始めた。頭の先は、白から。震えていた手が、ひと目ひと目編んでいくうちに落ち着いていった。
ボディの下三分の二は、オレンジ。指にはめてみると、もうすでに愛しい。
今朝、いや、ついさっき電話をもらうまでは、高知なのか、広島なのかで、暮らしている隆也を何度も想像していた。想像の中の隆也は、時には女性といたり、時には静かに笑っていたり、窓辺でぼんやりしていたり、どれも幸せそうだった。
もし女性といて、そこで家族のように暮らしていても、もう一度、帰ってほしいなどと自分は言えるのだろうか。そんな彼を見て、何かを問いただすなんてことはできるのだろうか。
また、気持ちがざわつきそうになり、カラフルな糸ばかりが収まったかごへと手を伸ばした。少しずつ編み続けているうちに、莉子ほどではもちろんないけれど、糸も色々に増えていった。先日、莉子からもらった毛糸玉が目に飛び込む。細くて白い糸にははじめからカラフルで小さなポンポンが無数に撚られてある。この糸をカナリヤ色の糸と合わせて編んでいくと、白やラメ糸も撚られた混ざり糸になる。
「こんな糸が、あるのか」
莉子の部屋で繁々と見ていると、
「使いかけでよかったら、あげるよ」と、ぽんと渡してくれたのだ。「もう結構、これ、使っちゃったから」と。
「編めるかな」
「ポンポンからやってみたら。合わせるだけで、単調な安い糸にだって、特別感が出る。最初は夢中になったけど、でもさ、ずっと使っていると、まだ素朴な糸に戻りたくなるんだよね。まずは、ポンポンから始めてみましょうか」
と、莉子は師匠っぽく気取って言った。
莉子の真似をして極端に大きなポンポンにしてみた。毛糸玉は直径十センチはゆうにある。それなりに見栄えのするポンポンにはなったが、縫い付けるのも難しく、頭の上から垂れ下がってしまう。ハサミで少しずつカットしていった。ポンポンは歪(いびつ)になり、整えているつもりが、どんどん小さくなっていく。今度は小さすぎるポンポンになり、やり直し。
もう一度固くポンポンを結び、頭のてっぺんにつけた。
頭の上で大きな花火が散っているような、眩しい、愛おしいパペット。
「こういう糸、なんて呼ぶの?」
「ぶーくれ」
莉子は口を突き出して、そんな音を出した。
「ぶくれ?」
「違う。フランス語、ブークレ、輪の意味」
それを思い出して、「ブークレ」、と発音してみる「ブークレくん、本物の花火、いつか見ようね」と声をかけてみるが、理玖は興味を示してもくれず、今日は床を這っている。這うことを覚えて、飽きずに這っている。編み物の手を離して、理玖のところにしゃがんで、抱き上げる。少し抵抗されるが、こちらを向いて笑ってくれる、私の天使。なのに、二人きりで隠れてしまおうとした私は、だめなお母さん。
ずっしり重みを増して、その少し湿った手で、母親の頬を面白がって叩く。持て余した力が、理玖から溢れ出してくるのを感じる。この数日、きちんと理玖と向き合ってこなかった。
「少し、お散歩に行こうか」
お散歩がわかるようで、床に降ろすと、扉に向かって全速力で這い出した。
(つづく)
▶次の話 「じゃあって何よ。いちいち腹が立つ」義母は背を向け、リビングの扉を開いた|うさぎの耳〈第八話〉谷村志穂
◀前の話 自分は何を言われても、義母を優しい人だと感じるべきなのだろうか。|うさぎの耳〈第八話〉谷村志穂

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。
あわせて読みたい
-

- 「ケンカばかり」「浮気もする」夫が突然死。失って「この人が心から好き」と気づいたワケ
- 大学時代から付き合い始め、結婚20年になる夫が帰宅途中に突然死した。夫とはケンカばかりで、付き合って…
- (All About)[旅]
-

- Q. ダイエット中でも間食をとっていい? おすすめの時間はありますか?
- 【管理栄養士が解説】「ダイエットに間食はよくない」と思っている人は多いはず。しかし、間食を上手に活…
- (All About)[果物]
-

- 大好きなニンゲンがいなくなった!! 泣きながら捜索し始めると…/異世界に行ったら謎の生物に可愛がられた話(2)
- ニンゲンイナイヨー / (C)河口けい/KADOKAWA人間も謎の生物も、み〜んな可愛い! 優しすぎる異世界に胸…
- (レタスクラブニュース)[動物]
-

- ちょっと贅沢な朝食で一日を始められる、名古屋・栄のベーカリーレストラン「IEN Bake house」へ
- 名古屋栄の大通り沿いにある「IEN Bake house(イエンベイクハウス)」は、モーニングからディナーまで楽…
- (ことりっぷ)[北海道]
-
- 君の涙に、僕だけが気づいていた。【恋味多めのホストごはん#9】
- スランプ中の少女漫画家・黒沼と、歌舞伎町No.1ホスト・咲也が繰り広げる、甘くてちょっとビターな同居ス…
- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.