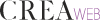【没後23年】“史上最強のテレビウォッチャー”ナンシー関とは何者だったのか? 「テレビ批評」と「似顔絵消しゴム版画」が遺したもの
コラムニストであり消しゴム版画家であり「史上最強のテレビウォッチャー」であったナンシー関さん(2002年没)。生前は、独特の観察眼による鋭いテレビ批評と著名人の似顔絵をユーモアたっぷりに彫った消しゴム版画で『週刊文春』や『CREA』など数多くの雑誌で才筆をふるいました。

亡くなって23年が経つ今年5月、「ナンシー関」の名づけ親であるクリエイターで作家のいとうせいこうさんプロデュースで、ナンシーさんが眠る青森県青森市の浅虫温泉にてトークと音楽の祭典「あさ虫温泉フェス」が開催されることに。昨秋、浅虫温泉の旅館「椿館」を訪れたいとうさんが、旅館のすぐそばにナンシーさんの菩提寺があると知り、ナンシーさんに捧げる「フェス」を発案したそう。
そんなわけで。いとうさんと、ナンシーさんの盟友でもある放送作家の町山広美さんが、ナンシーさんが暮らした部屋を訪れ、ナンシーさんの約5000点以上にも及ぶ消しゴム版画作品を管理する実妹・米田真里さんとともに、「ナンシー関とは?」を改めて振り返りました。(全3回)

テレビと距離を保ち続けたナンシー
いとう そもそもナンシーにどういう存在意義があったのかと考えると。少なくともテレビについてあんな風に語った人はいなかったんですよ、ナンシーがメディアに登場する1980年代半ば以前は。そのことを知らないと思うんだ、いまの人は。SNSの時代になり、全員が「ものを言う」ようになったから。
昔は、テレビに出ている芸能人・著名人に対して、あるいは、役者に対して、脚本家に対して、言わなかった、同業者しか。それをズバズバッと言ったのがナンシー。とにかくそれが新しい視点だったから、テレビの人たちはみんなオロオロしたと思うんだ。「え、俺たちそんなふうなの?」って(笑)。

町山 ナンシーさんは雑誌『ホットドッグ・プレス』で「ナンシー関」としてデビューしたわけですけど、いとうさんの「業界くん物語」(注:同誌の編集者だったいとうせいこうが担当していた連載。テレビやラジオ、広告、出版、音楽、ファッション業界などに携わる人々を紹介。ナンシー関もライターとして参加。86年に書籍化)という、業界ど真ん中の人たちの生態や仕組みを、業界周縁部の若者たちが徹底的に観察してイジってみせる企画が連載された場所なわけで。

ナンシーさんは、民放が2局しかない青森の出身で(注:現在は3局)、お昼の番組『笑っていいとも!』も夕方4時からの放送だった。なのにテレビは「1億2000万人、お昼です」なんて当たり前に大声で言ってて、ナンシーさんは「自分は埒外にいる」と。真ん中で何かやってるのを遠くから見ていたナンシーさんと、いとうさんの「業界くん」が、あの頃、雑誌というメディアで結びついたのは、本当に絶妙なタイミングだったと思っているんです。
いとう なるほど。その距離感だったからこそ、あの客観性を持ったのだ、と。
有名になってからも「テレビには絶対に出ない」って
町山 ナンシーさんのテレビとの距離感って、いとうさんもそうだけど、東京出身の我々とは全然違うんです。
私は東京の真ん中で生まれ育ち、中学は麹町だったんですが、『紅白歌のベストテン』の夏のプール大会の収録は学校の隣の赤坂プリンスだったので、ヒデキ(西城秀樹)の歌声が漏れ聞こえてくるという、その話をするとナンシーさんは「イヤな話」って言うわけですけど(笑)、私とヒデキの距離感と、夕方に『笑っていいとも!』を観る距離感には途方もない差があって。

しかもあの時代は、「業界」全体がうまくいっていたから、テレビの人たちは自分たちのコミュニティの中だけでやっていたし、外のことなんて誰も考えてなかった。そんなときに、声を上げたのがナンシーさんだった。
いとう コミュニティの外の外から言ったんだよね。「それ、ちょっとヘンじゃないの」と。
町山 そうなんです。「中」の人たちに「いやいや、私、お昼に観れてないし」って。
いとう その距離感こそがナンシーのキモだった。だから、ナンシーは有名になってからも「テレビには絶対に出ない」って言ってたのをよく覚えてるんだ。
――ナンシーさん、テレビに出たことってなかったでしたっけ?
真里 いえ、何回かはあるんですが、本当にもう、数える程度だったので。
町山 『タモリ倶楽部』とかNHK『婦人百科』の「消しゴム版画の年賀状の回」とか、ほんのちょっとだけ。

いとう 「出ると中に入っちゃうから書けなくなる」ってよく言ってたもの。
町山 やっぱり「中と外」の意識がナンシーさんにはあったし、あの頃のテレビにははっきりと境界線があった。だから、「外」のナンシーさんから「なにやってんだよ」って言われて初めて、「中」の人たちは「え?」って(笑)。
テレビの後ろ姿に目を向けた“視点の人”
いとう でも、そんな調子のいい時代ではあったけど、その距離感を踏まえ意識的に新しいテレビを作ろうとしていた人たちは少なからずいたわけで、「この部分に着目して書いてくれてうれしい」とナンシーを指針として番組を作ろうとしていたテレビマンも結構いたんですよ。
だから、ナンシーが知らないうちに、そんなつもりはまったくなかったのに、いつの間にかテレビに大きな影響力を与えていた、ということもあってさ。いま現在のテレビにおいて、そういう存在の人っているんだろうか? 的確な批評ができる人っているんだろうか?

町山 いまは、「中と外」がなくなり、境界線もなくなってしまったので、じゃあどの視点で書くのかというと、すごく難しい。若い人の多くは、どのチャンネルで何時にやってる番組か、番組タイトルさえも知らない。そもそもテレビは「流れてくる動画の1つ」でしかなく、昼の番組であろうが夜の番組であろうが関係ない。
しかも切り取りができちゃうから、それだけを受容してSNSで発言する人もいる。テレビが30分なり1時間なりの枠で放送しているという概念自体が崩れているから、なかなか話ができないのではないかと思うんですよね。

いとう そういう意味では、ナンシーはいい時代にいた、ということだ。テレビにとってもいい時代をナンシーに観てもらっていたし、ナンシーの視点で切り取ってもらうことで、2倍以上面白くしてもらったんだもの。
例えば、小野ヤスシさんの番組も、ナンシーの小野ヤスシ論を読んでから観ると途端に面白くなるわけじゃない(笑)。俺は小野ヤスシさんのいい加減な感じが好きだったし、芸能界の面白さを言えた人だったと思うけどね。
町山 さっき、真里さんが整理したナンシーさんのはんこをいとうさんと一緒に見させてもらい、ナンシーさんの自画像はんこもいくつか見ましたけれど、いとうさんが好きだというナンシーさんの自画像は、ナンシーさんがいちばん多く使っていたもので、斜め後ろの角度から見た自画像。自分からは見えない角度の絵なんです。

やっぱりナンシーさんは視点の人。それを自身も自覚していたからこその自画像だと思う。テレビの人たちは自分の後ろ姿を観られてるなんて思わずに放送してたわけだから、そこに目線を向けたというのはすごく大きかったと。
いとう 昔はさ、ドラマもみんな本気で観てたから、それが役者の芝居だとは思わなかったじゃない。その人が実は普段はごく普通の人で、お風呂も入るしトイレも行く、ということを考えなかった。後ろ姿がどういう人なのかを。でもナンシーはそれを見抜いていたということだ。
町山 やっぱり人って、何かを演じていたとしても、こぼれ出てしまうものだから、ナンシーさんはそれを見逃さなかったってことだと思うんです。
いとう 漏れ出ちゃってたんだ(笑)。
ナンシーの原稿には改行がひとつもなかった
町山 「見せたい私」が映っていると思い込んでる芸能人たちがいて、こぼれ出てるものを見逃さないナンシーさんがいる。よく「ナンシーさんが悪口を書いてた」って雑なことを言う人がいますけど、全然違う。
譬えがまた小野ヤスシさんになっちゃうけど(笑)、小野ヤスシさんは「見せたい小野ヤスシ」をテレビで出してるわけで、それを受けてナンシーさんは書くわけです。「こんなふうに見せたいんだろうけど、私にはこう見える」と。「小野ヤスシという人間がこうだ」と言ってるわけじゃない。

いとう 「もしもし、あなたが思うようには見えてませんよ」って、後ろから肩を叩くみたいな感じだよね(笑)。それをめちゃめちゃ熟考し、何回も何回も、それこそ消しゴムをかけて推敲していたわけだから、ナンシーは。最初は鉛筆で原稿用紙に書いていたからね。
ナンシーが書いたいちばん最初の原稿を取ったのは俺だったわけだけど、「ぱっくんぷれす」っていう『ホットドッグ・プレス』のコラムページでライターとして書いてもらったんですよ。
読者から送られてきたハガキを選び、面白いやつを引用して、「これは面白かった」というコラムを書いてもらったんだけど、原稿用紙にビッシリ、改行もなく、最後の「。」がいちばん最後のマスに入ってるの。ほんとビッシリ、何度書き直しをしたんだろうって思うほど。

それもすごくよかったんだけど、さすがに読みにくいから、「ナンシー、改行ってあんじゃん」って(笑)。「改行って、読む人がそこでちょっとひと息入れるためにあったりするから、もう一回書き直してくれない?」って言ったのをよく覚えてる。そのぐらいビッシリ書きたいことがある人だった。頭が熱くなるぐらい考えに考えて考え抜く人だったからね。
文=辛島いづみ
撮影=平松市聖
あわせて読みたい
-

- 豊田ルナ、「温泉旅行」をテーマにぬくもり感じるグラビア披露
- 豊田ルナが、4月28日(月)発売の「週刊SPA!」(扶桑社)の「グラビアン魂」に初登場した。 豊田ルナ「週…
- (GetNavi web)[温泉]
-

- 12星座別!2025年5月の金運は?【天秤座〜魚座】
- 2025年5月は金星が牡羊座、火星が獅子座という星の配置になります。牡羊座と獅子座はとても相性がよく、金…
- (All About)[イベント]
-

- 「夫との旅行はムリ!」“店構えでおいしいか分かる”と言い張る夫と2時間歩いた後の悲劇
- ゴールデンウイークを控え、旅行の計画を立てている人も多いだろう。だが、中には日常生活では問題がなく…
- (All About)[旅]
-

- 3,000円台でこの拡張力!UGREENの7in1USBハブ、正直“買い”です #Amazonセール
- 3,000円台でこの拡張力!UGREENの7in1USBハブ、正直“買い”です #AmazonセールImage:Amazon.co.jp こちらは…
- (Gizmodo Japan)[昆虫]
-

- エルヴィン・ヴルムさん、十和田で国内初の個展 「人のかたち」テーマに
- オーストリアを代表するアーティストの一人として知られるエルヴィン・ヴルムさんの個展「エルヴィン・ヴ…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[青森県]
-

- 三軒茶屋にカキ専門店「かきのおきて」 三陸産の生ガキを110円で提供
- カキ専門店「かきのおきて 三軒茶屋店」(世田谷区三軒茶屋2)がオープンして、5月1日で1カ月がたった。経…
- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東京都]
-

- スポーティーでありながら上品なデザイン!【シチズン】の腕時計がAmazonにて登場!
- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…
- (Walkerplus)[ファッション]
-

- GWのお出かけはここ!<サーティワンと日本橋三越本店が初コラボ>限定フレーバー&豪華サンデー、オリジナルグッズも見逃せない
- このゴールデンウィーク、サーティワン アイスクリームと日本橋三越本店が初のコラボレーションを実現! 4…
- (CREA WEB)[CREA WEB]
-

- ついに抗がん剤治療がスタート! SNSの力を借りて、副作用対策はバッチリです/33歳ママ、乳がんステージ3でおっぱいにサヨナラします(13)
- 困ったときのSNS!! / (C)ななぽよ/KADOKAWAイラストレーターで漫画家のななぽよさんは、愛する夫・もぽ…
- (レタスクラブニュース)[新商品]
キーワードからさがす
Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.