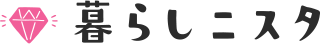「緑のgoo」は2025年6月17日(火)をもちましてサービスを終了いたします。
これまで長きにわたりご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
面接や会議がつらすぎる…。定型発達の人にはわからない〈発言の場で頭が真っ白になる人〉の理由とは【もしかして…発達障害!?】
「自分の順番が回ってきても、何も言葉が出ない」「発言を求められると、ドキドキして息苦しくなる」。これがいつものこととなると、発達障害の傾向がありそうです。
ディスカッションが超苦手。頭がフリーズしてパニック!!【ASD傾向】

「パニック」と聞くと、取り乱して泣きわめくような姿を想像する人も多いかもしれません。けれど実際には、外からは目立たない「静かなフリーズ」状態に陥るケースもあります。
目の前で次々にやりとりされる情報を処理しきれず、頭の中が真っ白になってしまうのです。
ASDの傾向がある人は、一度に多くの情報が入ってくると処理が追いつかず、「オーバーヒート」してしまうことがあります。
たとえば、1対1の会話であれば、言葉のやりとりは“キャッチボール”のようなもの。相手からの言葉を受け取って、自分の言葉を返す——それだけでも難しさを感じることがあります。
それがディスカッションとなると、難易度はぐっと上がります。
あちこちから一斉にボールが飛んできて、それを受け取り、返さなければならない。しかも、人数が多ければ多いほどボールの数も増え、混線します。ひとつの話題だったはずが、気づけば話題が次々に切り替わっていることも。
そうなると、どこからボールが飛んできて、どこに返せばいいのかがわからなくなり、頭の中はパンクしてしまうのです。
思い切ってカミングアウトすれば配慮してもらえるかも
何人もの話を同時に聞いて理解し、自分の意見をまとめて伝える——。そんな“コミュニケーション力”が求められるディスカッションや研修会は、ワーキングメモリー(いわば「記憶のおぼん」)の容量が少ないASDの人にとって、大きな負担になることがあります。
状況によっては、無理に参加しないという選択肢もあっていいでしょう。
また、可能であれば「ディスカッションが苦手なんです」と、あらかじめ伝えておく(カミングアウトする)ことで、配慮してもらえる場合もあります。
たとえば、「Mさんは聞くだけの参加で大丈夫です。意見はあとで紙に書いて提出してください」といった対応をしてくれる職場もあるかもしれません。
あるいは、本来5人のグループで話し合うところを3人にしてもらう、文章化された資料について意見を述べる形式に変えてもらうなどの工夫でも、負担感は大きく軽減されます。
配慮が受けられるかどうかは環境や状況によりますが、相談してみることで道が開けることもあるはずです。
▶次の話 聞いてた…?定型発達の人にはわからない〈話が通じない人〉の隠れた理由とは?【もしかして…発達障害!?】
キャリア約30年の精神科医が
発達障害による「生きづらさ」
の対策を徹底レクチャー!
部屋が片づけられない、約束の日時を間違える、集団から孤立しがち…など、あるあるな発達障害傾向と「ラクに生活するための考え方や生活のヒント」を伝授。「もしかして発達障害!?」の夫や子ども、仕事関係の人の理解にもつながる1冊です!

『もしかして発達障害?「うまくいかない」がラクになる』1,760円/主婦の友社 司馬理英子著
Amazonで詳しく見る 楽天で詳しく見るキーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.