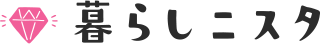【気候や気圧による不調】薬剤師は知っている3つの対策
「天気が悪い日は頭が痛くて気分も暗くなる」「どんよりとした日は、くらくらして家事をするのもつらい」。気圧が低くなると、このような症状に悩まされる人が増えるといわれています。今回は低気圧と不調の関係性と、気候に左右されない体質になるセルフケア方法を薬剤師が解説します。
気圧の変化が体調に変化を及ぼす原因
気圧の変化による体調不良は、からだの中の水分バランスや自律神経の乱れが主な原因といわれています。
耳のなかの、鼓膜のさらに奥に「内耳(ないじ)」という器官があり、その内耳は耳で受けた情報を脳や神経に伝える役割を担っています。
ただし、その内耳が気圧の変化を感知し、バランスをつかさどる「前庭神経(ぜんていしんけい)」が過剰に興奮することで、体調を崩してしまうのです。
これにより交感神経が優位になるとめまいや片頭痛が起き、副交感神経が優位になると、眠気やだるさを感じるといわれています。
気圧の変化によって起きる体調不良は?

気圧の変化によって起こる主な体調不良を4つ紹介していきます。
1.頭痛
気圧の変化によって体内の余分な水分が増えることで、血管が拡張し頭痛が起きます。
とくに脳内の血管が拡張すると周りの神経を圧迫してしまい、それにより炎症が引き起こされて頭痛を感じてしまうのです。
2.めまい
気圧の変化によって自律神経のバランスが崩れて交感神経が優位になると、めまいを感じる人もいます。
交感神経が優位になることで血管が収縮した状態が長く続くと、耳や脳に酸素や栄養が行きわたらなくなり、ふわふわとしためまいを感じてしまうのです。
3.眠気
気圧の変化によって自律神経のバランスが崩れて副交感神経が優位になると、眠気を感じやすくなります。
からだをリラックスさせる効果のある副交感神経ですが、気圧によって強制的に優位になると、起きていないといけない場面でも眠くなってしまいます。
また、低気圧になると上昇気流が起きているため空気が薄くなり、脳が酸欠状態になりやすくなるため、それにより眠気を感じる方もいます。
4.気分の落ち込み
自律神経のバランスが崩れると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくできなくなることで夜に眠れなかったり、リラックスすべきときにリラックスできなくなったりします。
これによりからだに負担がかかり、また、寝不足になりイライラしがちになることで落ち込んでしまう人もいます。
気圧の変化に対する3つの方法
冬に向けて気圧が低くなりがちな今の季節。ここからは、気圧の変化に対する方法を3つ紹介していきます。
1.耳・首のストレッチ

マッサージによって内耳の血流をよくすることで、低気圧不調の改善が期待できます。耳のストレッチの手順は以下の通りです。
1.親指と人差し指で両耳を軽くつまみ、上・下・横に5秒ずつひっぱる
2.耳を軽く横に引っ張りながら、後ろに5回ゆっくりと回す
3.耳を包むように前に折り曲げて、5秒そのままにする
4.手のひらで耳全体を覆い、後ろに5回ゆっくりと回す
耳に血液を送っている首の血流をよくすることで、耳だけではなくからだ全体の血行がよくなり、心身の不調が改善されるといわれています。
耳のマッサージだけでは効果が実感できないという方は、首を回してこりをほぐす方法も試してみてください。
2.自律神経を整える食事を取り入れる

自律神経のバランスを整える食事により、低気圧不調を乗り越えることも可能です。
たとえば、発芽玄米や味噌に多く含まれるGABAと呼ばれる成分はアミノ酸の一種で、神経のたかぶりを抑えてくれます。
また、豆腐や牛乳、チーズに多く含まれるトリプトファンは必須アミノ酸の一種で、精神を安定させたり、不眠を解消してくれる栄養素です。
ささみ肉に多く含まれる動物性タンパク質は、からだの機能を整える酵素やアミノ酸のもとになるため、からだの不調を改善する効果があるといわれています。
このように、自律神経を整える食材を普段の食事に取り入れることで、低気圧不調を軽減することができるでしょう。
3.漢方薬の服用

ストレッチや食生活の改善だけでは低気圧の不調が改善されない場合は、漢方薬の服用もおすすめです。
低気圧不調を改善する漢方薬は、以下の基準で選ぶといいでしょう。
・自律神経を整える
・水分の循環をよくして、脳や内耳のむくみを改善する
・イライラや神経の興奮を鎮めて、精神を安定さる
漢方薬は自然由来の治療薬として、低気圧による頭痛やめまいといった症状の回復だけでなく、根本から体質を改善することも得意としています。
低気圧不調に悩む人におすすめの漢方薬
低気圧不調に悩む方におすすめの漢方薬は以下の3つです。
・五苓散(ごれいさん):余分な水分を体外に排出し、めまいを改善する。
・苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう):体内の水分の偏在や代謝異常を整え、とくに上半身を中心に水分代謝をよくすることで、めまいやふらつきを改善する。
・半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう):胃腸が弱くて下肢が冷えやすい方の、めまいや頭痛、頭重感などの症状を改善する。
このように、漢方薬には低気圧不調の改善を期待できるものが多くあります。
しかし、低気圧不調の症状や、自分の体質に合わせた漢方薬を飲まないと効果が実感できないだけではなく、副作用に悩んでしまうこともあるでしょう。
そんなときは、自分に合った漢方薬を専門家に提案してもらうのがおすすめです。
〈この記事を書いた人〉あんしん漢方薬剤師 山形ゆかり●薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。15社以上のメニュー開発に携わり、現在は症状の根本改善を目指す情報発信を行う。
あわせて読みたい
-

- 北鎌倉の古刹の味を受け継いだ食事処「点心庵」。円窓のある坐禅堂でゆったりと過ごすひととき
- 北鎌倉の風情漂う古民家をリノベーションした「点心庵」。広々とした座敷の奥には静かな坐禅堂があり、円…
- (ことりっぷ)[スローフード,自然化粧品]
-

- 食事拒否、物を触り続ける。父親と姉に怒られても止められなかった「声」からの命令
- 無理って何よ!! / (C)もつお/KADOKAWA中高6年間を女子校で過ごした作者のもつおさん。元々人の視線を…
- (レタスクラブニュース)[健康食材]
-

- 大好きなニンゲンがいなくなった!! 泣きながら捜索し始めると…/異世界に行ったら謎の生物に可愛がられた話(2)
- ニンゲンイナイヨー / (C)河口けい/KADOKAWA人間も謎の生物も、み〜んな可愛い! 優しすぎる異世界に胸…
- (レタスクラブニュース)[動物]
-

- 11日(日)も西から天気下り坂 九州〜関東で雨 沖縄は警報級の大雨 次の週末も雨
- 11日(日)も前線の影響で、沖縄では警報級の大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や…
- (tenki.jp)[気象]
-

- Q. ダイエット中でも間食をとっていい? おすすめの時間はありますか?
- 【管理栄養士が解説】「ダイエットに間食はよくない」と思っている人は多いはず。しかし、間食を上手に活…
- (All About)[健康]
-
- 君の涙に、僕だけが気づいていた。【恋味多めのホストごはん#9】
- スランプ中の少女漫画家・黒沼と、歌舞伎町No.1ホスト・咲也が繰り広げる、甘くてちょっとビターな同居ス…
- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]
キーワードからさがす
Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.