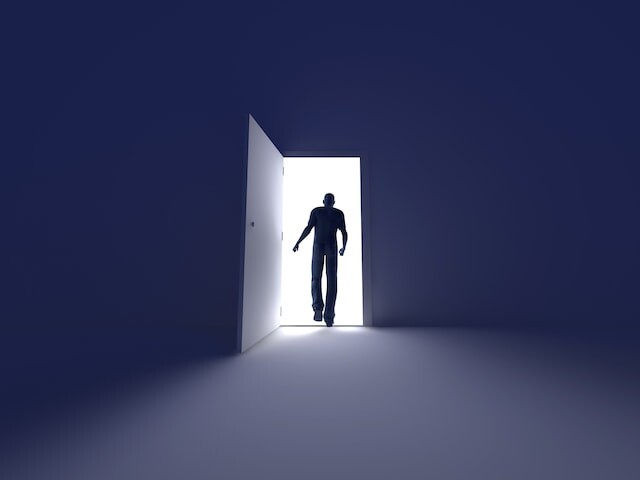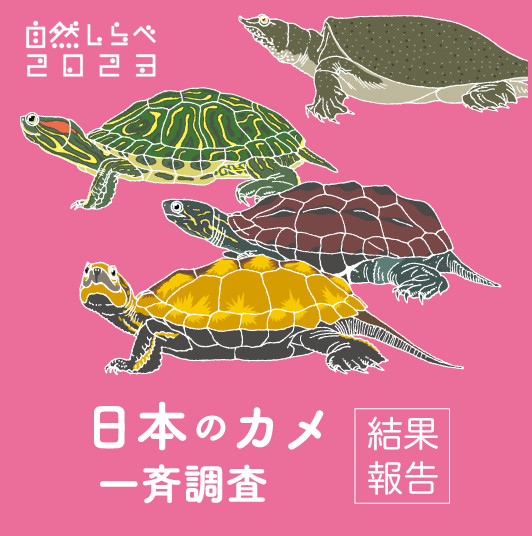この時期になると食べたくなるのがイクラの醤油漬けですよね。イクラとは鮭の卵のことですが、なぜこの時期がイクラの旬なのか? その理由を紹介します。

日本の鮭の正式名称はシロザケです。単にサケとも呼ばれます。ベニザケやギンザケ、カラフトマスなどもサケの仲間ですが、「鮭」と言えば、ほぼシロザケのことです。
シロザケは主に北海道や東北、北陸の河川で生まれ、稚魚は数週間、川で生活をした後に海へと降り、河口で数か月生活をした後にオホーツク海へと向かいます。その後、北太平洋~ベーリング海と広い範囲を回遊し、おおよそ4年前後でもとの川に帰ってきます。
母なる川に帰ってくる習性を「母川回帰性」といいますが、はるか数百キロもの旅路の末にもとの川に戻ってくる能力は驚くべきものです。川の近くにくると主に嗅覚に頼って母川を判別しますが、そこに至るまでには太陽コンパスや磁気コンパス、海流など様々な自然現象を利用しているといわれています。
日本にはおおよそ9~12月の間に母川回帰し、主に川に入る前のシロザケが近海で定置網などにより漁獲されます。その卵がイクラとして、その時期の食卓に並ぶというわけです。

海での漁獲を免れたシロザケは生まれた川を溯上しますが、多くの場合、河口近くに設置されたウライやヤナとよばれる罠で捕獲されます。それらは食用として、また翌春に放流する稚魚を育てるための親魚として利用されます。

ウライやヤナでの捕獲を免れたシロザケは、川の砂利底にメスが産卵床と呼ばれる巣を掘り、そこにオスがやってきてペアとなり、自然産卵を行います。
メスが卵を産む瞬間、オスは身体を寄せて放たれた卵に精子をかけます。そして産卵・放精を終えた卵は産卵床の隙間に収まり、メスによって砂利をかぶせられ孵化を待つことになるのです。

現在、私たちが食べている鮭やイクラの大部分は、人工ふ化放流されたシロザケが回帰してきたものといわれています。しかし近年、自然繁殖の再生産力が少しずつ見直されています。
そもそもシロザケを野生動物と見たとき、その自然な姿とは……?
そう考える風潮も、ここ数年で高まっているように感じます。


出典:わぉ!わぉ!生物多様性プロジェクト Facebookコラム
(2019年9月17日)
https://www.facebook.com/wow.wow.biodiversity.project/
※「わぉ!わぉ!生物多様性プロジェクト」は、公益財団法人日本自然保護協会とソニー株式会社が協働で実施しているプロジェクトです。
「わぉ!」という自然のおもしろさや不思議に触れたときの感動を多くの人に伝え、みんなで共有することで、自然を好きになってもらい、生物多様性の保全につなげていきます。